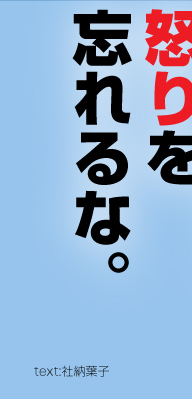僕はもう最初っからあきらめて生きてきた。自分が生まれ育った環境とか、血とか、もろもろ全部——。編集者・竹井正和さんが自分のことを語った著書『きょう、反比例』は、こんな言葉から始まっている。しかし、47歳の今、東京でアート系出版社を経営し、奈良美智や川内倫子、ロン・ミュエックなど世界中の気鋭アーティストと組んで仕事をしている。「向こうから本を作ってくれと言うて来る」と、にやり。「最初っからあきらめて生きてきた」という竹井さんが、どうやって今の自分にたどりついたのだろう。
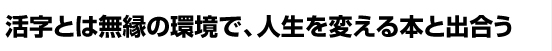
・・・竹井さんは、大阪市西成区にある被差別部落に生まれた。中国や韓国・朝鮮など在日外国人も多く住むこの地域は、当時、荒れに荒れていた。部落や在日外国人に対する差別のために、安定した仕事に就くのはきわめて難しい。結果的に生活が不安定になり、気持ちも荒れる。さらにその日暮らしで夢も希望も語れない大人たちを見て、子どもたちも「どうせ俺らなんか」と荒れる。
小学生の頃から友達と集団万引きや恐喝をした。高校時代はパンチパーマをかけてパチンコの腕を磨いた。「勉強しなさい」と言われたことは一度もない。何しろまともに字を読める大人自体が周りにいなかったから。漫画を読んでいたら「字、読んでるんか? 偉いなあ」と褒められた。家に本なんか、一冊もなかった。
どんな環境に生まれるか、人は自分で選ぶことはできない。被差別部落に生まれただけでなく、周囲の大人には何も期待できない、お金もない、学歴もない・・・「ないないづくし」のなかで子ども時代から青年期までを過ごした。
 コンプレックスはすごくあったよ。東京の出版社の編集者たちは、たとえば3歳からピアノを習っていたとか、膨大な量の本を読んできたのが当たり前。育ってきた環境の文化レベルが全然違う。文学、社会、経済、芸術の歴史や現在の状況・・・みんなが常識としてもっているものが、ぼくには何もない。その場その場で、自分にやれることを一点突破してきたようなもの。 コンプレックスはすごくあったよ。東京の出版社の編集者たちは、たとえば3歳からピアノを習っていたとか、膨大な量の本を読んできたのが当たり前。育ってきた環境の文化レベルが全然違う。文学、社会、経済、芸術の歴史や現在の状況・・・みんなが常識としてもっているものが、ぼくには何もない。その場その場で、自分にやれることを一点突破してきたようなもの。
そもそも編集者という仕事がどういう仕事であるかも知らなかった。どうにか高校を卒業してもその後の展望は何もなかった。小学2年生からやっていて、唯一得意だったそろばんを頼りに経理の専門学校に入って、同時に「きれいな先生がいる」と友人から聞いて英会話学校にも通い始めた。めっちゃデッカくて、めっちゃ自由だというアメリカに憧れた。
英会話学校の授業料は、そろばん塾の先生をして稼いだ。小中学生に「じゃかぁしいっ!」と怒鳴りながらも、うまくできない子にちゃんと教えてあげたいと思ってん。昔、ぼく自身が「できない子」だったから。
・・・ヒントを求めて入った本屋で、教育哲学者・林竹二さんの本と出合う。授業中もちゃんと座っていられない子どもたちと向き合おうとする姿に、心が震えた。本に登場する子どもたちは、まるで竹井さん自身だった。自分のために書かれた本だと思い、出版社の社長に「こんなすばらしい本を出してくれてありがとうございます」と手紙を出した。それがきっかけで経理として入社、その後、編集の実務を学んでいくことになる。

編集者になったのは、自分自身に何の才能もなかったから。そろばんをうまく教えたいとは思ったけど、教育者としての資質があるとは思えない。文章を書けるとか写真を撮れるとか、絵を描けるわけでもない。
ただちょっとだけ才能があるとすれば。人を見たり、話を聞いたりすれば、何となく「こういう人なのかな」とわかることだ。
それは生まれ育った環境の影響が大きいと思う。みんな、激しい気性だった。大人たちは一瞬で仲が悪くなったり良くなったりする。空気が一瞬で変わる。子どもたちはそれに翻弄される。ちゃんと空気を読み取らないと、とばっちり受けるねん。
平穏に見えるこの社会も、実は激しいものを抱えているよ。だけどそれを見せない。たとえば仲よくしていた人でも一度トラブルになったら、関係そのものをスッパリ切り捨ててしまう。トラブルが終わった時、ちゃんと仲直りして、また一緒に仕事ができるのか、それで終わるのかでは大きな違いだと思う。
・・・短く刈り込んだパンチパーマに、派手なシャツ。麻雀牌で作られたお気に入りのブレスレットが目をひく。否が応でも目立ち、職務質問を受けるのは日常茶飯事だ。怪しいと決めてかかってくる警察官は横柄で、いきなり突き倒されることもある。
「時間をとられるし腹も立ちますよね。めんどくさいから目立たない格好をしておこうとは思わないですか?」と訊くと、「ない!」とキッパリした答えが返ってきた。
 ぼくがどんな格好をするかは関係ない。怪しそうなやつを見つけたら職務質問をするのがおまわりさんの仕事なら、その仕事をする時にどういうふうな言い方をするかということ。「おまえ、どう考えても俺より年下やのに、なんでそんな言い方せなあかんねん」と、ぼくは怒るんですよ。「おまえ、何様?」って。 ぼくがどんな格好をするかは関係ない。怪しそうなやつを見つけたら職務質問をするのがおまわりさんの仕事なら、その仕事をする時にどういうふうな言い方をするかということ。「おまえ、どう考えても俺より年下やのに、なんでそんな言い方せなあかんねん」と、ぼくは怒るんですよ。「おまえ、何様?」って。
免許証でも何でも見せるけど、もちろん何も出てこない。「何やねん、俺が何かしたんか?」と言うと、やっと「すみません」と謝る。
いちいち言わないと、自分が偉いと勘違いする。「おまえは何も偉くない。たまたま警察官だから人を調べたりもするけど、おまえが偉いんじゃないよ」と教えてやらないと。警察官だけじゃない。政治家が偉いか? 医者が偉いか? 違うやろ。そういうことをきっちり言っておかないと。
作品を持ち込んでくる若い子たちにも「なんでもっと対象に踏み込まないの?」と突っ込む。びっくりするのは、就職活動で来る大学生たち。「本を読んでるか」と訊いたら、「読んでない」と。バットを振ったことのないやつが野球選手になれるか? 「ここはマイナーリーグじゃない。世界に打って出ようかという出版社なの。バットを振ったことのないおまえがメンバーになれるか?」と言うと、自分がまず何をすべきかがやっとわかる。
なんでいちいち突っ込むのかというと、ぼくは若い人達の可能性を信じたいんだよね。ぼくらの年代はもうおっさんで、可能性はなくなっていく。でも若い子には可能性もパワーもある。持って生まれた“運命”はそれぞれだけど、それをどう生かしていくか、人としてどう生きていくのかはみんな同じだと思う。その時、一番大事なのは、自分の頭で考えること。テレビや他人の言葉を簡単に信じたらだめ。自分の頭で考えて、判断して、動くことや。

・・・今でも忘れられないことがある。英会話学校に通っていた頃のこと。クラスメートのサラリーマンたちはよく会社の愚痴を漏らした。若い竹井さんが「そんなに言うなら会社辞めたらええやん」と言うと、「子どもがいるのに辞められるか」と口を揃えて言う。社会への疑問を口にすれば「おまえは青い!」「世の中、そんなに簡単に変えられるものじゃない!」と頭から決めつけられた。
「ほんまにそうか? やろうと思えばやれるはずや」という思いを、竹井さんはずっと忘れずに持ち続けてきた。せっかく就職した出版社を辞めて独立。話題作を次々出版しながら、高学歴の知識人や人脈がものを言うアート界に身ひとつで食い込み、「竹井正和の世界」を切り開いてきた。
 甘いだの青いだのと決めつけられた時、「ずるいなあ」と思ったよ。家族や社会のせいにしてるけど、絶対に逃げてるだけやと感じた。心得た大人のふりをして、何とも戦わず、いかに摩擦を起こさずに生きるかだけを考えている……「それが生きることなの?」と思いながらぼくは生きてきた。かといって無茶をしたわけじゃない。作家でも製版や印刷の職人さんでも、誠実に向き合うことを大事にしてきた。誠実にやってたら、人間、必ず通じる。 甘いだの青いだのと決めつけられた時、「ずるいなあ」と思ったよ。家族や社会のせいにしてるけど、絶対に逃げてるだけやと感じた。心得た大人のふりをして、何とも戦わず、いかに摩擦を起こさずに生きるかだけを考えている……「それが生きることなの?」と思いながらぼくは生きてきた。かといって無茶をしたわけじゃない。作家でも製版や印刷の職人さんでも、誠実に向き合うことを大事にしてきた。誠実にやってたら、人間、必ず通じる。
失敗は山ほどあります。ほとんどの本は、後で見ると「もうちょっとこうしたほうがよかったな」と思う。作ってる時はわからない。完璧なんてないよ。
でも売れるために妥協したことはない。こういう売り方をしたほうがいいというような方法論じゃなくて、自分が面白いと思うかどうか。自分の確信だけ。もちろん、小さい会社ながらも社員がいるし、ぼくには責任がある。売れなかったら会社が回らなくなるという不安はあるよ。
馬券を買うのと一緒かな。「これしかない!」と、ガーンと突っ込む。あとはプルプルしながら結果を待つ。負けた時は「あああ〜〜〜」と(笑)。でもプルプルしないと必死で考えないでしょう。必死やからこそ、「こいつはいけるか?」と自分の感覚を研ぎ澄ませるわけで。
・・・差別に敏感でありながら、部落解放運動などに関わることはなかった。しかし、部落出身者であることは片時も忘れたことはない。部落に生まれ育つ子どもたちへの思いも強い。
部落の環境は、昔に比べれば変わった。差別に対してものが言いやすくなっているのも確か。だけど「差別はいけません。差別をなくしましょう」といくら言っても、すべてなくすのは無理やね。
そんな社会のなかで生きる力をどうもっていけるかが大事になってくる。ぼくみたいに勉強ができなかったやつでも、生きる方法を見つけられた。みんなそれぞれに何かあるはずだということを伝えたい。自分に誇りをもって生きてほしい。
部落解放運動みたいに、集まって政治的な力をつけることも必要だと思う。だけど一人で闘うことも大事だし、みんなが同じことをする必要もまったくない。それぞれの場所で、それぞれががんばったら、世の中変わってくる。それこそが「解放運動」と違う? これがすごく大切やねん。

|