ふらっとへの手紙 北出新司さん from貝塚 vol.1
2015/04/17

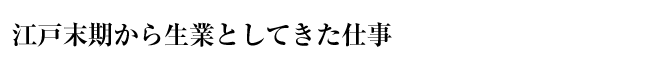
ぼくは家族とともに大阪府貝塚市で精肉店を経営しています。うちは代々屠畜を生業としてきました。ぼくは7代目で、初代まで遡れば江戸末期になります。古文書によると、今ぼくたちが暮らす地域は江戸時代には岸和田藩に属し、「嶋村」と呼ばれていました。そして病気や怪我でたおれた牛や馬の処理を担い、また皮をなめして馬具や武具など道具を作っていたようです。肉も塩漬けや燻製にしていたようですが、当時は肉食が禁止されていたこともあって主な目的は"倒れ牛馬"の処理でした。
冷蔵庫のない時代、大きな動物を解体したり皮をなめしたりすると匂いもあるし、周囲は汚れます。そのことが人々の「穢れ意識」につながり、地域ぐるみで差別を受けていました。いわゆる「被差別部落」です。周辺から排除され、明治以降も就労や結婚をはじめ、日々の暮らしのなかでもさまざまな差別を受けていました。たとえば地元の学校への通学が許されず、ムラ(ぼくたちは自分たちの地域をムラと呼びます)の寺に4年制の小学校をつくって子どもたちに教えていました。大正初期に統廃合され、ようやくほかの地域の子どもたちと一緒の小学校に通えるようになったのです。

一方、肉食が定着するなかで地域の仕事も牛や豚の飼育や屠畜へと移行してきました。ぼくの家でも牛を飼い、肉にするという仕事で生計をたててきました。多くの人は何らかの仕事をしてお金を稼ぎ、生活をしています。ぼくたちにとってはこれが自分たちの仕事であり、何も特別なことではありません。けれど「屠畜」つまり牛を割る(ぼくたちは"殺す"ではなく"割る"と表現します)部分がことさらにクローズアップされ、「残酷」「かわいそう」「汚い」と言われるのです。その理不尽さを子どもの頃から感じてきました。
20代で家業を継ぎました。ぼくたち夫婦と姉や弟も一緒にやってきました。一方、食肉の世界は時代の流れとともに全国的に変化してきました。屠場の統廃合と大規模化、機械化が進み、地方の小さな屠場はどんどん閉鎖されてきました。ぼくたちのムラの屠場もすでに貝塚市営となっており、市の施設として経営状態が問われるようになっていました。要するに「収益をあげられているのか」ということです。当時の市長は「歴史的な背景や地域の産業を支える観点から収益の側面だけで判断すべきでない」としていましたが、ムラでも飼育から屠畜、精肉まで一貫しておこなう家が年々減り、施設の老朽化もあって1990年代から屠場の閉鎖は時間の問題でした。そしてついに2012年3月に閉鎖が決まったのです。

そんな時、映画監督の纐纈あやさんからぼくたちの仕事を映画にしたいという申し出がありました。『屠場』という写真集を発表した本橋成一さん(写真家、映画監督)とのつながりでぼくの弟と知り合った纐纈さんは、牛が肉に変わっていく光景やその技術、働く人たちの姿を映像に残したいと考えていたようでした。たまたま知り合ったぼくの弟の話を聞き、うちまで来て屠場や店を見て「ぜひ撮らせてほしい」と言われました。ドキュメンタリーですから、ふだんの生活や家族の様子も含めて、です。
正直、最初はとまどいました。まず、ぼくらの仕事や生活が映像になるのか?という疑問です。そして閉めることが決定していた古びた屠場やすべて手作業でおこなうぼくらのやり方を今の時代にあえて見せることに「恥ずかしいなあ」という気持ちもありました。しかし監督もあきらめません。家族で何度も話し合い、最終的には受け入れることにしました。ただ、ぼくたち家族だけでなく、差別のことや部落解放運動に対する取り組み、そしてムラの文化も含めて撮ってほしいと話しました。監督も了解してくれ、2011年秋からたくさんの人を巻き込んだ映画づくりが始まりました。(2015年4月談)

