ふらっとへの手紙 北出新司さん from貝塚 vol.3
2015/05/15

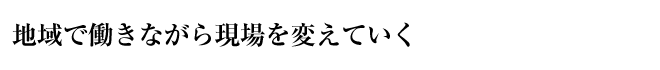
ぼくが水平社宣言と出会った頃、地域に部落解放同盟の支部と青年部ができました。ぼくも先輩たちとともに青年部で活動を始めます。1969年に成立した同和対策事業特別措置法を受け、社会の経済的発展から取り残されていた被差別部落の環境はみるみるうちに改善されていきました。
一方で、人々の心にある差別は根強くあり、地域の先輩もつきあっている女性との結婚の際、差別を受けました。地域のなかには「騒ぐから差別される。下手に運動などせず、真面目にやっていれば差別はなくなる」といういわゆる"寝た子を起こすな"という考えをもつ人も少なからずいました。ぼくたちは「でも寝てる子はいずれ起きるんだよ」と粘り強く働きかけながら運動を広げてきました。
運動組織が大きくなるにつれ、専従として働く人が増えてきました。研究者やメディアの人たちも組織に入ってきました。ぼくは地域の役員になりましたが、専従になるつもりはありませんでした。さまざまな立場の人が部落差別の解消に向けて行動するのはいいことです。しかし解放運動そのものは"専門家"だけがやるものでない。地域で働きながら、その現場を変えていくのが運動だというのがぼくの考え方です。地域が変わるということは自分や自分の家が変わるということ。もちろんその先に「差別をなくす」という大きな目標があるわけですが、まずは自分の足元から変えていくという思いです。やがて弟や姉も運動に加わりました。
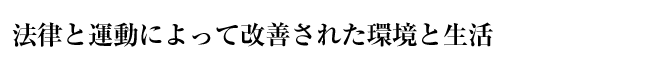
親父は「なんでおまえらだけが苦労せなあかんねん」と、ぼくたちが運動することに反対でした。けれど地域の環境が変わっていくにつれて運動の力を感じたようです。住宅が建ち、奨学資金制度や固定資産税の減免制度がつくられ、苦しかった生活がある程度は楽になりました。一番大きかったのは奨学資金制度です。ぼくが高校進学した時に始まった制度で、授業料と定期代が出て本当に助かりました。こうしたなかで、部落解放運動に参加することが損にはならないと感じた人は多かったと思います。ただ、そこに差別にどう立ち向かうか、どんな地域をつくっていくのかといった意識改革が伴っていたかというと疑問も残ります。それは運動の責任です。
親父は口癖のように「汚れた仕事しててもきれいにしてたらいいんや」と言い、身なりには気を遣っていました。「人を泣かせて飯食ったらあかん」とも言っていました。だまされてもだましたらあかん。商売でいいかげんなことをしたらあかん----。教育を受けていないことや職業で差別されながら、その口惜しさを自分なりの商売の鉄則としていたのでしょう。親父に限らず、差別の痛みや口惜しさを一人ひとりが耐えながら体を張って生きてきた時代が長く続きましたが、差別は社会の問題だという共通認識がようやく生まれたのでした。
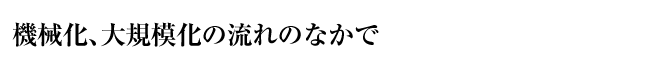
一方、食肉店の経営は楽ではありませんでした。父の代から始めた牛の飼育は弟が引き継ぎましたが、高度経済成長とともに食肉産業も流通も機械化、大規模化が進んでいきます。ぼくたちの地域には日本でも最大級といわれた「泉南家畜市場」があり、最盛期は1日1200頭の取引がありました。父親はここで牛を買い、自分で飼育し、すぐ近くにある貝塚市立屠畜場で屠畜して販売する卸業をしていたわけです。しかしそうした食肉の"地産地消"は大きな流れに飲み込まれるように衰退しはじめました。
ぼくたちは経営を卸から小売りに切り替えました。小売りは大きく儲けることはできませんが、自分たちが動けば確実にお金が入ってきます。自分たちが飼育して割った食肉を冷蔵ケースつきの車で移動販売するというアイディアが当たり、経営を軌道に乗せることができました。当時は約25頭の牛を飼い、1ヶ月に2頭のペースで屠畜していました。映画にもその場面が出てきますが、牛を割る日は弟が屠畜場まで牛を引き、ハンマーで倒した後はぼくたち夫婦と姉、弟夫婦とで手分けして割っていきます。600kgから800kgもある牛を倒すのは命がけの真剣勝負だし、切り分けて洗浄や掃除をするのにも体力や神経を使います。割った瞬間から食肉としか見ないと前回書きましたが、その根底に「命をいただく」という意識、だからこそ一片も無駄にしないという思いは常にあるのです。(2015年4月談)

