子ども
- 2004/01/29
一人でも多くの子を幸せに 里親30年、60人の子を育てて -
-
別れの悲しみよりも巣立ちの喜び
 若い頃は経験も浅いため、幼い子ばかりを預かった。「言葉も文字も私たちが教えました。するとその子にとっては私たちの家が“ふるさと”になるんです。“きょうだい”もいるから楽しい。だから実のお母さんが引き取りに来ると嫌がるんですね。押入れに隠れたりしているのを無理やりお母さんに渡すと、すがるような目で私たちを見るんです。それが本当につらくて、こんな思いをするならもう止めようと何度も思いました。ところが女性は強いですね。家内に“もっとつらいのは子どものほうや。あんたは止めたらそれでいいけど、里親が必要な子どもはどうするの”と怒られました」と利夫さんは苦笑する。隣りでサヨコさんが言葉を添える。「人間は裸で生まれて裸で死んでいくもの。どんな出会いにも必ず別れがあるんです。ただ、私たちは(別れが)早いんですね。早い子で1週間、長期でも5年10年経ったら別れないといけない。一生のうち何十回という別れがある。でも別れるたびに悲しんでいてはいけないと思うんです。子どもが成長して巣立っていってくれる、と私は受け止めています。無事に巣立ちができたら、里親として本望なんです」
若い頃は経験も浅いため、幼い子ばかりを預かった。「言葉も文字も私たちが教えました。するとその子にとっては私たちの家が“ふるさと”になるんです。“きょうだい”もいるから楽しい。だから実のお母さんが引き取りに来ると嫌がるんですね。押入れに隠れたりしているのを無理やりお母さんに渡すと、すがるような目で私たちを見るんです。それが本当につらくて、こんな思いをするならもう止めようと何度も思いました。ところが女性は強いですね。家内に“もっとつらいのは子どものほうや。あんたは止めたらそれでいいけど、里親が必要な子どもはどうするの”と怒られました」と利夫さんは苦笑する。隣りでサヨコさんが言葉を添える。「人間は裸で生まれて裸で死んでいくもの。どんな出会いにも必ず別れがあるんです。ただ、私たちは(別れが)早いんですね。早い子で1週間、長期でも5年10年経ったら別れないといけない。一生のうち何十回という別れがある。でも別れるたびに悲しんでいてはいけないと思うんです。子どもが成長して巣立っていってくれる、と私は受け止めています。無事に巣立ちができたら、里親として本望なんです」
利夫さんが「別れがつらい」と弱音を吐いた時、里親と子どもとをコーディネートしている人が「里親というのは野に咲く日陰の花。だから美しいんです」と言ったという。中学生でも抱っこして愛情を伝える
限られた時間だからこそ、“親”としてできる限りのことをしてやりたいという強い思いが永井さん夫婦にはある。基本的な生活習慣を身につけさせるほか、回転寿司やファミリーレストランなどに連れ出し、家と外との区別や公共の場でのマナーを教える。現在預かっている兄弟は熊本で開かれる里親の全国大会に連れてゆく。なかなか乗る機会のない飛行機に乗せてやりたいからだ。兄弟は大喜びで心待ちにしている。「長い期間預かる子には、ここにいる間に忘れられない思い出をひとつはつくってやりたいと思っているんですよ」と利夫さん。
預かる子どものほとんどは何らかの“心の傷”を抱えている。親と暮らせないこと自体が子どもにとっては悲しいことだが、虐待による痛手を負った子も多い。
「テレビや新聞で報じられる虐待は身体的虐待が多いですが、ウチへ来る子は精神的虐待を受けた子が多いんです」と利夫さんは顔を曇らせる。サヨコさんは子どもの傷の深さを感じると、たとえ中学生であっても抱っこして寝ることがある。「小さい時に愛情が欠けると、ずっと心に空洞を抱えたまま生きていくことになります。するとおとなになってから今度は周りの人への愛情が欠けてしまう。いったん愛情が欠けた時期まで遡って、十分に心を満たして初めて体と心の成長が一致するんですよ」
中学3年で永井家に来た男の子は、心の優しい子だった。好き嫌いもなく、弟たちの面倒もよく見たが、ひとつだけ「これだけはやめてほしい」と言ったのが「牛丼」だった。幼い頃に両親が離婚し、父親に引き取られた。ずっと食事は1日1食で、チェーン店の牛丼ばかり食べていたという。「牛丼も最初はおいしかったでしょう。ただ牛丼とともに思い出されることがイヤなんだと思います」。離れて暮らしていた母親は「就職するなら一緒に暮らす」と言ってきた。就職を希望した彼に永井さん夫婦も協力し、中華料理店への採用が決まった。社会へ巣立つ子どもにはいつも「まるでお嫁に出すような」支度を整えて送り出すのが永井家の常である。サヨコさんは下着から服、靴まで揃えた。そうして「幸せになってほしい」という願いとともに送り出した彼が、就職直後に無断欠勤を重ねた末に行方不明になってしまった。母親は他人とワンルームの部屋で暮らしていた。思い描いていた生活とはかけ離れたものだったのだろうと利夫さんとサヨコさんは推測する。「連絡してほしい」というサヨコさんの願いも空しく、今も行方はわからない。「ウチでの生活はあくまで予行練習みたいなもの。本当の幸せは実の親との生活のなかにある。幸せを夢見て帰ったのに何もかも壊れてしまった」と利夫さんは今も口惜しがる。荒れた子どもが抱えていた傷
 中学生になってどうしようもなく荒れたという少女を預かったこともある。父子家庭に育ち、学校へ行かなくなって手を焼いた父親が施設に託した。それでも学校へ行かないからとさらに永井さん夫婦に託されたのである。ところが永井家に来たとたん、1日も休まず登校を始めた。とても明るくなり、人が変わったようだと担任も驚いたという。学校から帰ると、利夫さんに「おとうさーん」といって抱きついてくる。外を歩くと小さな子たちと争って利夫さんの腕をとりにくる。普通なら恥ずかしがったり照れたりする思春期の子がなぜ……と利夫さんは不思議だった。
中学生になってどうしようもなく荒れたという少女を預かったこともある。父子家庭に育ち、学校へ行かなくなって手を焼いた父親が施設に託した。それでも学校へ行かないからとさらに永井さん夫婦に託されたのである。ところが永井家に来たとたん、1日も休まず登校を始めた。とても明るくなり、人が変わったようだと担任も驚いたという。学校から帰ると、利夫さんに「おとうさーん」といって抱きついてくる。外を歩くと小さな子たちと争って利夫さんの腕をとりにくる。普通なら恥ずかしがったり照れたりする思春期の子がなぜ……と利夫さんは不思議だった。
「後でわかったことですが、その子は実のお父さんから虐待を受けていたんです。親に裏切られたという思いがあるから施設へ行っても荒れた気持ちが収まらなかった。ところがウチへ来たら、お父さんお母さんがいて、きょうだいもいる。子どもとして甘えられる場所ができて、やっと落ち着いたんでしょう」。こうした深い傷を負った子を何人も見てきた。「精神的な虐待は表に出ませんし、罪にもならない。でも何とかならないのかなあ」。どんなに心を尽くしても、親権をもつ親にはかなわない。利夫さんたちは何度もやるせない思いを噛みしめてきた。
父親から虐待を受けていた彼女は高校を卒業し、就職。やがて仕事を通じて知り合った男性と恋愛結婚をした。1年後には生まれたあかちゃんを抱いて訪ねてきてくれた。
利夫さんとサヨコさんは、送り出した子どもたちに自分たちから連絡をとることはしない。“親心”が、自分の力で生きる道を切り開いていかなくてはいけない子どもたちの足を引っ張ることになってはいけないからである。助けを求められたら飛んで行くし、訪ねてきてくれるのは大歓迎。けれど「日陰の花」はでしゃばってはならない。利夫さんがふと「ウチらは本当に親なんかなあ」と漏らした時、サヨコさんは「預かっている時は必死に親をやってるのよ。その時は間違いなく親なんよ」と応えたという。そんな切なさもあるからこそ、幸せな姿を見せに来てくれるのが何よりうれしい。利夫さんは「“日陰の花”でも子どもたちが光を当ててくれる」と満面の笑みで言う。 - 関連キーワード:









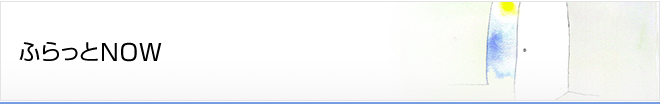
 若い頃は経験も浅いため、幼い子ばかりを預かった。「言葉も文字も私たちが教えました。するとその子にとっては私たちの家が“ふるさと”になるんです。“きょうだい”もいるから楽しい。だから実のお母さんが引き取りに来ると嫌がるんですね。押入れに隠れたりしているのを無理やりお母さんに渡すと、すがるような目で私たちを見るんです。それが本当につらくて、こんな思いをするならもう止めようと何度も思いました。ところが女性は強いですね。家内に“もっとつらいのは子どものほうや。あんたは止めたらそれでいいけど、里親が必要な子どもはどうするの”と怒られました」と利夫さんは苦笑する。隣りでサヨコさんが言葉を添える。「人間は裸で生まれて裸で死んでいくもの。どんな出会いにも必ず別れがあるんです。ただ、私たちは(別れが)早いんですね。早い子で1週間、長期でも5年10年経ったら別れないといけない。一生のうち何十回という別れがある。でも別れるたびに悲しんでいてはいけないと思うんです。子どもが成長して巣立っていってくれる、と私は受け止めています。無事に巣立ちができたら、里親として本望なんです」
若い頃は経験も浅いため、幼い子ばかりを預かった。「言葉も文字も私たちが教えました。するとその子にとっては私たちの家が“ふるさと”になるんです。“きょうだい”もいるから楽しい。だから実のお母さんが引き取りに来ると嫌がるんですね。押入れに隠れたりしているのを無理やりお母さんに渡すと、すがるような目で私たちを見るんです。それが本当につらくて、こんな思いをするならもう止めようと何度も思いました。ところが女性は強いですね。家内に“もっとつらいのは子どものほうや。あんたは止めたらそれでいいけど、里親が必要な子どもはどうするの”と怒られました」と利夫さんは苦笑する。隣りでサヨコさんが言葉を添える。「人間は裸で生まれて裸で死んでいくもの。どんな出会いにも必ず別れがあるんです。ただ、私たちは(別れが)早いんですね。早い子で1週間、長期でも5年10年経ったら別れないといけない。一生のうち何十回という別れがある。でも別れるたびに悲しんでいてはいけないと思うんです。子どもが成長して巣立っていってくれる、と私は受け止めています。無事に巣立ちができたら、里親として本望なんです」 中学生になってどうしようもなく荒れたという少女を預かったこともある。父子家庭に育ち、学校へ行かなくなって手を焼いた父親が施設に託した。それでも学校へ行かないからとさらに永井さん夫婦に託されたのである。ところが永井家に来たとたん、1日も休まず登校を始めた。とても明るくなり、人が変わったようだと担任も驚いたという。学校から帰ると、利夫さんに「おとうさーん」といって抱きついてくる。外を歩くと小さな子たちと争って利夫さんの腕をとりにくる。普通なら恥ずかしがったり照れたりする思春期の子がなぜ……と利夫さんは不思議だった。
中学生になってどうしようもなく荒れたという少女を預かったこともある。父子家庭に育ち、学校へ行かなくなって手を焼いた父親が施設に託した。それでも学校へ行かないからとさらに永井さん夫婦に託されたのである。ところが永井家に来たとたん、1日も休まず登校を始めた。とても明るくなり、人が変わったようだと担任も驚いたという。学校から帰ると、利夫さんに「おとうさーん」といって抱きついてくる。外を歩くと小さな子たちと争って利夫さんの腕をとりにくる。普通なら恥ずかしがったり照れたりする思春期の子がなぜ……と利夫さんは不思議だった。