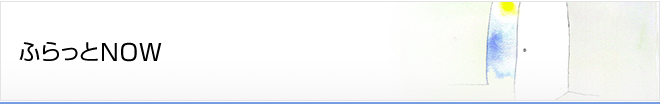福祉・医療
- 2008/02/07
映画「新・あつい壁」 ハンセン病問題はまだ終わっていない -
-


大学で映画制作について学び、卒業制作として脚本を書く段になって浮かんだのは「ハンセン病」だった。「ハンセン病を正しく理解できる映画をつくりたいという思いとともに、人をあっと言わせるものを作りたいという気負いもありました」。取材のため、夏休みに生まれ故郷へ帰り、恵楓園を訪ねた。療養所の医師から改めて、大人には決して感染しないことや感染したとしても治る病気であることなど、十分な説明を受けた。ところがいざ取材を始めようとすると、職員用トイレのノブすら触れることができない自分がいた。
「大人になるにつれて、思っていることと行動とが違う人間になっていたんですね」。脚本どころではない。自分のなかにある差別意識と格闘が始まった。「入所している人の部屋を訪ねたら、お菓子を出してくれました。私は甘いものに目がないんですが、その時は砂を噛むようでした。それで、水をもらって流し込んだんです」。湯飲みで水を渡してくれた人の手が震えていた。「当時は外からの訪問者にお茶などを出さないというのが、暗黙の“マナー”としてあったように思います」訪問者をもてなすのに痛々しいほど気を遣う入所者と、正しい知識をもちながら体で拒否反応を示してしまう自分。正義感に燃え、勢い込んでいた中山さんは、自分の偽善や欺瞞につくづく嫌気がさした。もって行き場のない自分への嫌悪感を振り切るように、入所者と一緒に入浴したこともある。「患者さんたちはびっくりしますよね。私のほうは気持ちいいわけですよ。これで俺も差別者ではない、と。患者さんは優しいから、“うれしかばい”と言ってくれる。ますます気持ちいい」。しかしものの5分と経たないうちに、「違う」と思った。「頼まれて風呂に入ったわけではないのに、“ハンセン病のあなたたちと一緒に風呂に入ってあげているんだ”という思い上がりの、新たな差別意識があるのに気づいたんです」。一瞬でもいい気になった自分がますます嫌になった。
どうにか脚本を書き上げたが、自分との格闘は続いた。大学卒業後も療養所へ通い、入所者たちとの交流を深めながら自分のなかにある差別意識と向き合った。卒業制作の脚本を元に映画『あつい壁』が完成した時、32歳になっていた。
そんな中山さんだからこそ、理屈や正論では差別が解消できないことを知っている。「交流するなかで少しずつ理解、共感していくしかない。言葉は適切じゃないかもしれないけど、“慣れ”も大事です。ハンセン病は手足が曲がったり、顔が変形したりするという後遺症があるんですが、それも交流するうちに慣れて馴染んでくる。最終的に差別を乗り越えるために必要なのは、理屈や知識ではなく、交流と共感なんです」
今回の『新・あつい壁』も、ハンセン病問題を知らない人や解決したと思っている人にとって、ハンセン病問題を改めて知るための出会いになることを願っている。 - 関連キーワード: