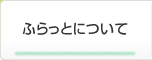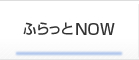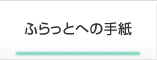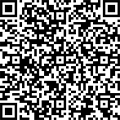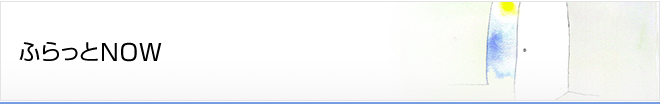子ども
- 2010/06/22
僕にできるのは、子どもたちに寄り添い共に生きること 1998年1月、「第3次覚せい剤乱用期」に日本が突入したという宣言が政府から出された。この時、いちばんの問題点とされたのが、10代の中高生を中心とした若者に集中的に薬物が入っていることだ。実際に1994年の推定統計で70万人だった覚せい剤乱用者が、2003年1月には160万人(警察庁発表)に急増。そのうち7~8割が10~20代だという。定時制高校で社会科を教える水谷修さん(47歳)も、若者をむしばむ薬物汚染と闘い続けてすでに12年になる。
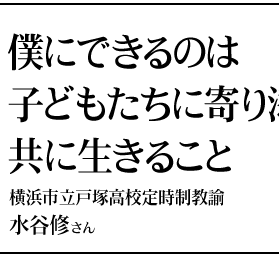
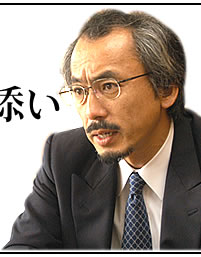
子どもたちが心配なだけ
水谷さんの1日は長い。授業を終えた夜の11時頃、繁華街に「夜回り」に出る。たむろする少年・少女たちに「早く帰れ」と声をかけ、「困ったら連絡しろ」と自宅の電話番号を刷り込んだ名刺を渡して歩く。薬物や非行から若者を守るための深夜のパトロールだ。
帰宅後もひっきりなしに掛かってくる薬物相談の電話。もっとも多いのが夜中の2時だという。今年に入って直接の電話相談だけで約600件。直接介入しているのが175件。授業前の午前中と休日を利用して年間約300回の講演をこなし、今も全国に薬物で1,800人余り、非行も含めると約4,000人の子どもと関わっている。
「ただ子どもたちが心配なだけ。子どもたちのそばにいて共に生きるのが僕の仕事です」「明日の青少年を創るんだ」と熱く燃えて高校教師になった水谷さんが、自ら夜間高校に移ったのは13年前。いきなり任命されたのが生徒指導部長だった。問題を起こす生徒たちと関わるなかで、彼らの背後にいつも見え隠れするのが大人の陰。水谷さんは子どもたちを「花の種」にたとえる。
「どんな種であろうと、植えた人間が愛おしく丁寧に育てれば、花の咲かない種はない。もし咲かないなら、踏みにじられたか、水や栄養が与えられなかったか・・・。そう、その子たちは大人がつくった社会の被害者なんだ」
そうした子どもたちの前に立つのは自分しかいない。子どものそばにできるだけ寄り添えば、いずれ分かってくれるという気持ちで続けてきた「愛の生徒指導」。家庭が恵まれず非行を繰り返す子は、自宅に2~3週間一緒に住まわせる。そうすれば、どんなに突っ張ってる子でも変わっていった。「あんたが殺したんだ」
 そうした愛の指導で限界にぶつかったのが「薬物」だった。12年前、シンナー漬けの教え子(当時16歳)に死なれてしまった。
そうした愛の指導で限界にぶつかったのが「薬物」だった。12年前、シンナー漬けの教え子(当時16歳)に死なれてしまった。
彼の父親は暴力団員で、組の抗争で彼が3歳の時に死亡。母親は暴力団関係者と離れ、貧しくともパジャマの縫製工場で働きながら彼を育ててきた。その母親が寝込んで働けなくなり、彼は給食の余ったパンと牛乳をもらうことで食べ物を確保しようとして、いじめを受けるようになる。それを助けたのが同じアパートに住む暴走族の少年で、彼は小学6年からその仲間に入ってしまったのだ。それをとても哀しんだ母親。母の気持ちを察した彼は心の傷をうめるためにシンナーに手を出してしまい、4年間も使い続けていた。
その彼が「シンナーを止めたいから先生のそばにいたい」と、共に暮らすようになるが、家に戻すとまた吸い始めてしまうという生活を3カ月ほど繰り返していた頃のこと。
彼が、「先生じゃシンナー、やめられない。俺をここへ連れて行ってくれよ」と、薬物治療専門病院の新聞の切り抜きをもって現れた。その言葉にいらだち、「来週連れていくから」と辛くあたって帰らせてしまった。それから、わずか4時間後。シンナーからくる幻覚で、両手でライトをつかむようにダンプカーに飛び込んで事故死してしまった。
「僕が追いやった死でした」
彼の母と2人だけの寂しい葬式。有機溶剤であるシンナーは大脳新皮質の外部や歯、骨を溶かしてしまう。シンナーでボロボロになり、おまけにシンナーを体内に入れたまま焼かれた彼は、骨すらほとんど残さなかった。箸ではサラサラと崩れて拾えない遺骨を、泣きながら両手ですくった。
一週間後、自分が犯した過ちを整理したいと訪れた薬物治療の病院の医師からズバリ言われてしまった。「水谷さん、あんたが彼を殺したんだ。ドラッグをやめられないのは依存症という病気なんだ。病気が愛の力で治るのか」と。この出会いが、薬物との12年に渡る闘いの原点となった。
「薬物の知識があれば、彼は死なずにすんだかもしれない」
以来、薬物依存症について勉強を重ね、全国の専門病院や関連施設、警察へと人脈を広げていった。- 12
- 関連キーワード: