|
|
 |

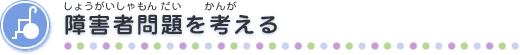 |

実地で覚える盲導犬の訓練
「ジェイ、ゴー」「ジェイ、グッド」「グッドボーイ、ジェイ」・・・。菅 庸起(すが・つねき)さん(40歳)は訓練中、絶えず犬に声をかけながら歩く。うまく角を曲がったり、止まっている車をよけたりできれば、必ずほめながら頭や身体をなでてやる。そうやって犬は自分の役目を覚え、自信をつけてゆく。毎日毎日、雨の日も休まない。菅さんにとっても、犬にとっても、実に根気のいる作業だ。
菅さんはそれを「小学生の5分間ドリル」に例える。「いっぺんにはやれないんです。毎日、同じことをちょっとずつ繰り返す。地道にコツコツやるうちに覚えるんです」
 菅さんの肩書きは、盲導犬指導員。盲導犬の訓練だけでなく、視覚障害をもつ人の相談にのったり、盲導犬に対する理解を深めるための講演などにも出かける。
菅さんの肩書きは、盲導犬指導員。盲導犬の訓練だけでなく、視覚障害をもつ人の相談にのったり、盲導犬に対する理解を深めるための講演などにも出かける。
盲導犬育成のカリキュラムも育成する人の呼び名も、団体によって異なり、国家資格はない。国内の8団体のうち唯一の社会福祉法人(他は財団法人)である日本ライトハウスでは、盲導犬訓練士と盲導犬指導員に分かれる。採用されるとまず、「盲導犬訓練士」として盲導犬の育成に専念。犬の世話から接し方、訓練法など一通りのことを覚え、盲導犬として通用する犬に育てあげる。教科書があるわけではなく、先輩からひとつひとつ実地で教わっていく。ある程度の実績を積むと、相談業務や講演活動もする「盲導犬指導員」として認められる。一人前の訓練士になるのに平均3年かかり、5年を過ぎた頃に指導員となる人が多い。 盲導犬として使われる犬は、ラブラドールレトリバーあるいは、ゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーのミックスがほとんど。基本的に人間が好きでおっとりとした性格であり、体格がよくて病気に強いという性質が盲導犬向きだといわれている。それでも人それぞれ性格が違うように、犬にも個性がある。育つ過程で大きなショックを受けるようなことに遭遇し、性格に影響する場合もある。 盲導犬として使われる犬は、ラブラドールレトリバーあるいは、ゴールデンレトリバーとラブラドールレトリバーのミックスがほとんど。基本的に人間が好きでおっとりとした性格であり、体格がよくて病気に強いという性質が盲導犬向きだといわれている。それでも人それぞれ性格が違うように、犬にも個性がある。育つ過程で大きなショックを受けるようなことに遭遇し、性格に影響する場合もある。
菅さんいわく、盲導犬に必要な要素とは「穏やかで作業意欲が高く、人間が好きなこと。それから環境が変わっても動じず、攻撃的でなく、臆病でもないこと・・・」と実に厳しい。もちろん最初からすべてを備えた犬がいるわけではなく、冒頭のように人と犬が一体となって、根気よく訓練を重ねて身につけていくのだ。
|
「犬が好き」だけではできない
「『犬が好きだから』とこの仕事を志望してくる人もいますが、仕事として犬と向き合うことが必要なんですよ。自分が育ててきた犬が、視覚障害をもつ人の家族の一員となるという意識を忘れてはいけない。だから時に、犬が好きだからこそつらい思いもします」と菅さん。それでは盲導犬訓練士には、何が求められるのだろうか。「まず、感情のコントロールですね。自分の感情をできるだけ入れずに犬と接します。盲導犬として必要な技術を、感情抜きにほめたり注意しながら教える。犬の好き嫌いもあるけど、心のなかで『相性悪いな』と思っても絶対、態度には出さない。それから健康管理がきちんとできること。訓練は毎日あるし、みんな自分の担当があるから、健康を保つのも仕事のうちです。そして、探究心。生き物相手の仕事ですから、正解はありません。どうしたらうまくいくのかを、いろいろ考え、試してみる気持ちが大事です」
 そう話す菅さんだが、実は彼自身も「犬が好きだから」とこの世界に飛び込んだ。大学卒業後に就職したのは、大手アパレル会社。デパートに派遣されたが、数字だけで評価される世界にどうしてもなじめなかった。ちょうど1年勤めた後に退社。再就職先を探してめくっていた就職情報誌に、日本ライトハウスの訓練士を紹介する記事が載っていたのがきっかけとなった。
そう話す菅さんだが、実は彼自身も「犬が好きだから」とこの世界に飛び込んだ。大学卒業後に就職したのは、大手アパレル会社。デパートに派遣されたが、数字だけで評価される世界にどうしてもなじめなかった。ちょうど1年勤めた後に退社。再就職先を探してめくっていた就職情報誌に、日本ライトハウスの訓練士を紹介する記事が載っていたのがきっかけとなった。
「募集はしていなかったんですけど、『バイトでもボランティアでもいいから』と食い下がりました。数字じゃなくて、生き物を相手にする仕事がしたかったんです。『じゃあ、名前だけ聞いておくから』と言われたので、自宅近くの住宅展示場で警備や清掃のアルバイトをしながら連絡を待ってたんですよ」。2ヵ月後、たまたま一人の訓練士が辞めることになり、菅さんに幸運がめぐってきたのだった。「よく『素晴しいお仕事ですね』と言われますが、実際には地味で単調なことの繰り返しです。もちろん悩みもあります。それでも一度も辞めたいと思ったことがないのは、犬が好きだからというよりも、前の仕事を経験したからかもしれません。実は今でも、前の仕事の夢を見てうなされることがあるんですよ。ハッと目が覚めて『よかった、夢だった』と安心するんです。自分に合わない仕事に苦しんでいた時よりは、ずっといい。福祉のことなんか何も知らなかったけど、現場でいろいろなことを実感し、学んだという感じですね」
日本ライトハウスでは、年間30頭の盲導犬を育てるのが精一杯というのが現状だという。しかしその何倍もの人が盲導犬を待っている。「私たちの課題は、いかに安定したレベルの盲導犬を、安定して供給できるかということ。そのためには素質のある子犬と、それを育てる人材が必要なんですが、社会的な環境や経済的な面で難しいところです」
菅さんは今後、訓練士の養成にも力を入れていきたいと考えている。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- 社会福祉法人 日本ライトハウス
- 行動訓練所(盲導犬訓練部)
〒585-0055
大阪府南河内郡千早赤阪村1202
TEL:0721-72-0914/FAX:0721-72-0916
法人本部
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中2ー4ー37
TEL:06-6961-5521/FAX:06-6968-2059
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|

盲導犬以外にも、警察犬や災害救助犬など人間のために活躍する犬は多い。最近は「介助犬」の存在も知られるようになってきた。介助犬とは、その名の通り「肢体不自由な人の日常動作を介助する訓練を受けた犬」。ドアの開け閉めや、床に落ちたものを拾う、荷物を口にくわえて運ぶなど、さまざまな日常動作をこなす。'92年、アメリカで訓練された犬がやってきたのがきっかけで日本でも知られるようになり、'95年に国内で育成された介助犬第一号が誕生した。
しかし何といっても歴史が浅く、まだまだ知名度は低い。盲導犬のような法的な認可もされていないため、公的支援が一切なく、外出先で出入りを拒否されるケースも多い。「介助犬をそだてる会」の事務局次長、西田英夫(にしだ・ひでお)さんは、「マスターさん(ユーザー。介助犬を必要とする人)のもっている障害によって必要な介助が違ってくるため、介助犬の訓練には多くの費用と時間がかかります。まだ全国でも12、3頭しかいません。介助犬を育成しながら、その存在をより多くの人に知ってもらい、社会的に認められるように働きかけていくのも私たちの役目です」と話す。
 介助犬育成団体は国内にいくつかあるが、盲導犬と違って団体同士の連携体制も整っていない。また介助犬専門の訓練士もおらず、家庭犬や警察犬のトレーナーに委託し、手探りで訓練をしているのが実情だ。'95年に設立された「介助犬をそだてる会」では、会員の会費や募金、バザーなどの収益金で運営を行い、育成した介助犬を無償でマスターに貸し出している。代表の坂根毅彦(さかね・たけひこ)さんは、こう話す。「介助犬は、できないことをやってくれる『ロボット』ではありません。愛情を持って接するうちに犬と精神的なつながりができ、心の支えになります。なでたり、散歩することがリハビリにもなります。犬を連れて歩くと声をかけてくる人がいて、人とコミュニケーションがとれます。犬がいるだけで、行動範囲、人間関係が広がり、生活が明るくなるんです。
介助犬育成団体は国内にいくつかあるが、盲導犬と違って団体同士の連携体制も整っていない。また介助犬専門の訓練士もおらず、家庭犬や警察犬のトレーナーに委託し、手探りで訓練をしているのが実情だ。'95年に設立された「介助犬をそだてる会」では、会員の会費や募金、バザーなどの収益金で運営を行い、育成した介助犬を無償でマスターに貸し出している。代表の坂根毅彦(さかね・たけひこ)さんは、こう話す。「介助犬は、できないことをやってくれる『ロボット』ではありません。愛情を持って接するうちに犬と精神的なつながりができ、心の支えになります。なでたり、散歩することがリハビリにもなります。犬を連れて歩くと声をかけてくる人がいて、人とコミュニケーションがとれます。犬がいるだけで、行動範囲、人間関係が広がり、生活が明るくなるんです。
これから社会の高齢化が進むにつれて、高齢者にとっても大きな存在になっていくと思いますよ」
犬を「利用する」のではなく、犬をパートナーとして認めることを、マスターはもちろん、社会にも求められいる。
|
このページの一番上へ 
|



