|
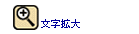
熊手麻紀子さん、36歳。中学2年、小学6年と3年の子どもたちの母親として主婦として奮闘しながら、お産や助産婦(師)のサポーターとして活動してきた。自身は助産婦(師)の温かいケアを受けながら喜びに満ちたお産を経験したものの、多くの女性が「思い出したくない経験」としてお産を語るのに愕然とし、「何かおかしい、このままじゃだめだ」と立ち上がったのがきっかけだった。
資格も仕事ももたず、一貫して「ケアを受ける側」として発言や情報発信をしてきた熊手さんだからこそ見える、お産をする女性が置かれている現状と助産婦(師)への思いを語ってもらった。
※ 2002年に「保健婦助産婦看護婦法」が一部改正され、保健婦は保健師、看護婦は看護師、助産婦は助産師となりました。男女で名称が違ったのを統一する、専門家イメージの強い「師」を使うなどの理由があります。けれど熊手が出産された当時は「助産婦」であり、熊手さん自身は「助産婦」という名前に意義と敬愛をもっているため、文中では「助産婦(師)」とさせていただきます。

・・・年々、出産数が減少するなかで、病院や産院はお産をする女性の気持ちに敏感にならざるを得ません。また、雑誌やインターネットなどにはさまざまな病院や産院の紹介やアピールがされています。つまり、以前よりもずっと選択肢が増え、お産に対する女性の意識も変化してきているようなイメージがあるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
確かにそう見えますよね。でも実際のところはどうでしょう? というのも、お産を「いい思い出」として話してくれる人が本当に少ないんですよ。フルコースの料理だとか有名ブランドのバスタオルだとかエステだとか物質的なメニューは増えても、本当に人間的なケアまではたどり着いていないように思います。「あなたに一番必要なものは何? エステじゃないよね。人が人としていられる、あったかいケアのなかで産むことじゃないかな」と問いかけて初めてハード面だけが重要なんじゃないと気づく人もいますが、なかなか……。景気が悪いといっても、やっぱりみなさん、結構ぜいたくで快適な生活をしてるじゃないですか。その延長で、痛みを避けたり、設備や食事にこだわったりするんでしょうね。
・・・「こだわり」といえば、バース・プラン(妊婦が希望するスタイルに添ったお産をする)もそのひとつでしょうか。最近、よく耳にします。
 「バース・プラン、やってます」という看板を掲げる病院が増えていますね。でも妊娠したばかりの人に「どんなふうに産みたい?」と唐突に聞いても答えにくいと思います。具体的な体験談を聞く機会がなければイメージがわかないし、お産をワクワクと楽しみに待つ気持ちにもなかなかなれないでしょう。「どう産みたいのか、わからない」「どう育てればいいのか、わからない」というのは仕方ないんです。ちいさな子どもが身近にいないんだもの。 「バース・プラン、やってます」という看板を掲げる病院が増えていますね。でも妊娠したばかりの人に「どんなふうに産みたい?」と唐突に聞いても答えにくいと思います。具体的な体験談を聞く機会がなければイメージがわかないし、お産をワクワクと楽しみに待つ気持ちにもなかなかなれないでしょう。「どう産みたいのか、わからない」「どう育てればいいのか、わからない」というのは仕方ないんです。ちいさな子どもが身近にいないんだもの。
バスや電車のなかで親子連れを見かけても、「かわいい」とは思っても心に根付くものはあまりありませんよね。やっぱり親戚のお姉ちゃんにあかちゃんが生まれたとか、近所のおばちゃんちでまた生まれたとか、人間関係のあるところでの子育てを体験していないと。性教育の講演で学校へ行った時には子どもたちにいろいろ質問するんですけど、ある時、高校生に「この1年間で、あかちゃんに触れたか、身近な人があかちゃんを抱っこしているのを見たことがある人は?」って聞いても、誰も手を挙げない。そうやって育ってきた人たちが「お母さん」になるんですね。
だから、女性は妊娠したら大忙しなんですよ。覚えなきゃいけないこと、考えなきゃいけないことが一度にきて。
| |  |
|


