|
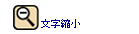
子どもに恵まれなかった若い夫婦が養子縁組を思い立った。紹介された待望の子どもを抱いて喜びにひたるうち、「ウチの子だけが幸せになってええんやろか」という思いがムクムクとわいてきた。以来30年、あかちゃんから高校生までの約60人の子どもを預かり、育ててきた。そんな永井利夫さん・サヨコさん夫婦が語る、子どもたちへの愛と“親子”の絆。
生活習慣やマナーを教えることから始まる
町工場が立ち並ぶ大阪市東淀川区。新幹線の高架脇に利夫さん・サヨコさん夫婦が経営する工場兼住居がある。1階が工場で2階が事務所、さらに階段を上ると子どもたちの声が響く住まいである。日当たりのいいダイニングの真ん中に10人は座れる大きなテーブル。ここで日々、にぎやかな会話や笑顔、きょうだいゲンカが繰り広げられているのだ。
取材当日、永井家の子どもは高校1年生の男の子から4歳の女の子まで5人。両親が離婚し、働くのに精一杯の母親から預かっている兄弟や両親ともに亡くした子、母親のお産を控えた子など、事情はそれぞれに違う。永井さん夫婦はやって来た子どもを温かく迎え入れつつ、その子の表情や態度、食事の様子などを注意深く見守る。子どもたちには分け隔てなく接するが、配慮する部分はそれまでの生活や親との関係によって違うからだ。特に食事の場面では、どんなふうに育ってきたかが顕著に表れる。「自分の好きなものだけ食べる。ちいさい子なんかはデザートを最初に食べるんです。親が子どもに基本的なことを教えていない、叱っていないことがわかります」と利夫さん。サヨコさんがご飯とおかずを交互に食べ、栄養のバランスを考えて嫌いなものも食べるようにと辛抱強く教える。
 |
| 食堂に貼られた「永井家の11か条」。みんなで守るルールは、その時々の子どもたちと永井さん夫婦が話し合って決める |
厳しい口調になると、「お母さん、怖いからキライ」と言い出す子もいる。利夫さんに「耳、貸して」と言い、「私、お母さんのことキライやねん」と打ち明けた女の子がいた。外へ出かける時は「お父さんとお手々つないで行くからね」と内緒で約束させられるのだが、サヨコさんが「行くよー」と呼びかけると真っ先に「はーい」とついて行く。「いつも僕は裏切られるんです」と利夫さんは笑うが、厳しさのなかの愛情を子どもが敏感に感じ取っている証ともとれる。一方、サヨコさんは利夫さんに「子どもに甘い」と怒る時もあるが、子どもたちには「いざという時にはお父さん」という姿勢を見せている。普段は穏やかな利夫さんだが、子どもたちが羽目を外しすぎた時には思い切り叱る。子どもたちも心得たもので、サヨコさんには乱暴な言葉づかいをしても、利夫さんに対しては一歩控える。小言も言うが甘えを受け止めてくれる「お母さん」と、細かいことは言わないかわりに怒ると怖い「お父さん」。“両親”に見守られ、子どもたちは元の生活に戻ったり社会へと巣立つ時に困らないよう、基本的な生活習慣やマナー、公の場でのルールを学んでゆく。
乳児院で出会った子どもたち
永井さん夫婦は、東京オリンピックが開かれた1964年に結婚した。子どもを待ち望んだが恵まれずにいた結婚9年目、利夫さんが里親を募集する新聞記事に目をとめた。当初は乗り気でなかったサヨコさんだが、夫婦で乳児院に出かけ、0歳から2歳までの子どもたちに接するうちに血縁にこだわる気持ちが消えていった。やがて当時1歳の女の子を養子候補にと紹介された。ところが永井さん夫婦の顔を見るたびに泣く。利夫さんは当時のことを今もハッキリと覚えている。「お菓子をあげようとしても受け取らないし、バイバイしても無視する。嫌われたのかなと寂しい思いをしながら乳児院に通い続けました。ところがある日、私のことを“おとう、おとう”と言ってくる子がいたんです。思わず抱き上げようとすると、うちの子が飛んできて、“どけ”というようにその子を押しのけようとする。あの時はものすごく感動しました。初めて私らに気持ちを表現してくれた。あんな感動はありません」。揺らいでいた気持ちがしっかりと定まった瞬間でもあった。半年後、永井さん夫婦は晴れて“親”になった。
ところが、親子で仲良く暮らすうちに「ウチの子だけが幸せになっていいのだろうか」という疑問がわいてきた。乳児院で暮らす幼い子どもたちの姿が目に焼きついて離れない。「みんなウチで育てられたらいいんだけど、そういうわけにもいかない。でも何とか一人でも多くの子どもを幸せにしてやりたいという気持ちが出てきました。娘にもきょうだいが必要だし。それで養育里親をすることになったんです」と利夫さん。以来、約30年の間に60人以上の子どもたちを育ててきたのである。
|


