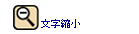
「自分の話しか出来ませんけど」と言いながら、インタビューに応じてくれた女の落語家、桂あやめさんの2回目の登場。「“男の落語”に近づくよりも、“女”のままで演じた方が自然な笑いを取れた」「落語会では、全体の流れの中での自分ポジションに与えられた役割を果たさなければ」・・・。男と女の生き方にもつながる、含蓄のある話を伺いました。
女の落語家は損?
落語は、創作するのも演じるのも聞くのも男の人で続いてきた世界ですから、男の人用にしか作られていません。女や子どもが出てくる話もあるので、はじめのうちは自分なりにそういうのを演じようとしたんですが、まるで歌舞伎の女形の化粧や動きのように不自然になる。「男の人が演じるための型にはめられた女」を女が演じると、余計に女から遠ざかってしまうんです。
だから、男の落語家が落語をやるよりも、笑いにつながるまでが遅い。たとえば、マクラの部分で、「文枝の12番目の弟子です。しばらくおつきあい願います」と言っている時は、お客さんは私のことを女だと思って聞いているけど、続いて「こんにちは」「あ、おまはんかいな」と古典落語に入った時、この会話が男同士のものなのか、それとも女のものなのかと疑問を持つ。安心感がないから、笑っても「ふふふ、でも何で?」という感じになる。女は損や、と思いました。
化粧して演じる創作落語
 そこで、私は男の格好をしようと思って、ショートカットに縞柄の着物の着流しなど男装をして高座に上がったり、無理に低い声を出したりしてみたんですが、そうするとよけいに男か女か分からず、どんどん不自然な方向へ行く。私自身が男装するなど男の人として生きているのならそれもいいんでしょうが、普段は化粧も口紅もしたいという人間だから、これは違うなぁと思った。
そこで、私は男の格好をしようと思って、ショートカットに縞柄の着物の着流しなど男装をして高座に上がったり、無理に低い声を出したりしてみたんですが、そうするとよけいに男か女か分からず、どんどん不自然な方向へ行く。私自身が男装するなど男の人として生きているのならそれもいいんでしょうが、普段は化粧も口紅もしたいという人間だから、これは違うなぁと思った。
あるいは、登場人物を男から女に入れ替えて演じようとすれば、江戸時代や明治時代には植木屋や大工には女がいなかったし、遊廓に行った帰りに「腹へったなぁ、うどんでも食おか」という話(『時うどん』)なんかも成り立たない。その時代の女の人を描くなら、髪結いさんや子守り奉公、井戸端で起こる騒動になるやないですか。それやったらいっそう、「今の時代を切り取った自分の言葉を話したい」と思うようになり、自分の周りにいる面白い女の子を主人公にした落語を作ってみよう、と。女子大生ネタやOLネタ、化粧品売り場ネタなどの新作を作って演じることにしたんです。
女の着物を着て化粧、マニキュアもして高座に上がると、私も楽で、自然に演じられる。お客さんもすっと、そのまま話の中に入ってくれる。男の真似をして演じるより、結局、自然に女のままで演じるのが一番良かった。発明は不便でないと出来ないというけど、ほんま、そうやなあと思います。今では演じる落語の90%以上が創作落語です。


