 |
男女双方への差別の禁止 |
 |
今回の改正で注目すべきことの一つが、女性保護という福祉的な意味合いのある「女性に対する差別禁止」から、本来の法のあるべき姿とされる「性差別禁止」にステップアップしたことだ。
「そもそも21年前の最初の均等法制定の時に、『性差別禁止法』にすべきだという意見も強かったのですが、企業側、経営者側のコンセンサスが得られず、実現しなかった経緯があります。今回の改正で、ようやく本来の意味での性差別禁止が実現したのです」
と、松井さんは言う。
従来は、女性に対する募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇についての差別が禁止されていたに過ぎなかったが、改正法ではこれらを男女双方に対する禁止事項とすると共に、男女双方に対する禁止事項として降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職勧奨、労働契約の更新が新たに加えられた。
Q1「以前、応募したかったA社の求人に『男性向きの職種』と書かれていたので、理由を聞くと、『当該部署は全員が男性なので、女性を採用しても部署に溶け込めないだろうから』と言われ、諦めたことがあります。こういった表記は禁止なのでしょうか」(31歳、女性)
この質問に、松井さんは「99年の改正法施行以後、性別を指定して求人することは完璧に禁止されています」。A社は女性に「配慮」しているつもりでも、これは「排除」に当たる。職場に溶け込めるかどうかは、「個人の問題」。女性求職者のチャンスを奪うことになる。求人に一定の資格が必要ならば、そう表記すれば良い、と言う。
男性女性がこれと逆の場合(『女性向きの職種』などの表記から、男性を排除する場合)も同様で、求人の記載にあたって、「女性(男性)歓迎」「女性(男性)向きの職場です」などの表現も禁止。応募する・しないを決める権利は、求職者側が有さなければならない。従来、いわゆる「男性職場」だった運輸、建設など夜勤のある職場で、トイレなど女性用設備がないケースでは、それらの設置も企業の責務となった。
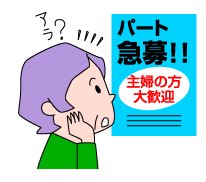 Q2「勤務時間10時〜16時の電話受付のパート募集に、『主婦の方歓迎』という表記を、以前見ましたが・・」(46歳、女性) Q2「勤務時間10時〜16時の電話受付のパート募集に、『主婦の方歓迎』という表記を、以前見ましたが・・」(46歳、女性)
このような微妙な表記は、結果的に「主婦」の方=「女性」を求めていると判断され、均等法違反となる。昼の時間帯のパートタイムの求人への応募は主婦が多いかもしれないが、男性がいないとは言いきれない。そもそも、「男性向き・女性向き」の価値観の転換が望まれている。
「日本では、求人に、配偶者や子どもの有無、学歴など『属人的』な要素での判断がされやすい。『その業務が出来るかどうか』のモノサシだけで十分なはずです」(松井さん)
本来、求人はその業務の遂行を自分がいかに可能かを示す「プレゼンテーション力」が問われるものであるべきである。「ふらっと」では、以前、ケント・ギルバートさんへの取材で、アメリカでは、市販の履歴書はなく、応募者が自分をアピールするために必要と判断することだけを、オリジナルの書式で作成するのがルールで、性別、年齢、人種など差別につながる判断基準になりかねない記載をしないのが鉄則だと聞いた。「日本の市販の履歴書に家族欄は消えましたが、性別や配偶者の有無等の記載欄があること自体、問題です」と松井さんは指摘する。
Q3「某支店の係長代理の役職が廃止されることになり、Aさん(男性)には別の部署の同等の役職が用意されたが、既婚で子どものいるBさん(女性)は一般社員に降格となりました。Bさんは、「(男性と同じ部署への配属は)勤務時間の関係から不適だと判断された」と言っていたが、後輩として納得できないのですが・・」(金融関係、20代)
これは、Bさん自らが望んだ結果であれば良いが、望んでいないのに会社の一方的な判断であるなら、明らかに「性差による取り扱い」「不利益の発生」に当たる。
Q4「当社では、 パートから正社員への変更にあたって、女性は『家族の了解書』を提出することになっています。正社員になると残業が増えるので、女性の場合は夫の了解を得ている方が残業をしやすいのではないかという見地からとのことですが、なんだかすっきりしません」(書店、30代)
Q5「男性社員には約2年ごとに配置換えがありますが、女性社員にはありません。女性は勤続年数が短いので、同じ部署で同じ職種に長く就くほうが効率的だとの判断からだそうですが・・・」(不動産関係、30代)
Q4については、「論外です。日本的家族主義の制度がもたらした悪しき慣例、誤った判断です」と、松井さんはきっぱり。
Q5について、「合理的な理由」があるかどうかが争点になるが、男女の性差による「配置替えの有無」に合理的な理由があるとは考えられず、女性に配置替えをしないのは、長く勤続したい女性のキャリア形成を阻むことにもつながるという。
いずれも、雇用側がいかに「女性のために」といった理由をつけようとも、本末転倒の「誤った“思いやり”」以外の何者でもない。ほかに、「リストラにあたって、事務職の契約社員は女性を優先して雇い止めをする」「女性(男性)を優先して退職勧告する」などの禁止も法律化された。
|


