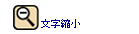

テレビを見ていて、ジェンダーの視点から「あれ?」と思うことはありませんか?
最近、メディアからの情報を必要に応じて分析するなどして読み解く力「メディア・リテラシー」が必要だと言われていますが、承知のとおり、巨大な影響力を持つテレビというメディアは、私たちのものの見方をつくっているといっても過言ではありません。
そんな中で、気になるのがテレビ番組を作る現場。関西の民放OGらで組織する団体「放送と女性ネットワークin関西」が設けた「女性が制作した、幅広い視点を生かした番組」を表彰する「WNB賞」最優秀賞の受賞歴のある、読売テレビ報道記者、十河美加さん(33)に、「放送とジェンダー」につながる話を聞きました。

----テレビを見ていると、たとえばアナウンサーなどに、男性は年輩者も多いのに、女性は比較的若い人ばかりだと感じます。実態はいかがですか?
弊社のケースで言えば、私は1994年の入社で、同期19人のうち、女性は6人。もちろん男女同条件での採用です。1986年の男女雇用機会均等法の施行以前に採用された女性が現時点では少ないこともあり、読売テレビ全体の嘱託・特別嘱託含む社員数は男性408人、女性89人※です。
専門職であるアナウンサーにも、86年以前に採用された女性が現在少ないわけですから、「テレビに出ている女性は若い人ばかり」という印象を持たれるかもしれません。しかし、最近では放送局全体で、しっかりニュースを読める40~50代の女性アナウンサーが必要とされてきているという話も耳にしますので、女性アナウンサーの平均年齢は徐々にあがっていくと思います。
----十河さんが所属されてきたのは、ずっと報道部?
そうです。最初は事件、事故から展覧会まで遊軍的に動く“何でも屋”でしたが、入社翌年に震災が起こり、震災報道の担当に。続いて、警察回りを2年弱。その後、記者に戻って、早朝のニュース番組や少しやわらかい情報番組を担当。2002年から、深夜12時台の「NNNドキュメント」のディレクターを務めています。
----一連の仕事をされてきた中で、男女の差を感じたことはありますか。
仕事上で、女性だからといったデメリットを感じることはまったくありませんでした。むしろ、医療や震災、犯罪についての報道を担当する中で、もっと違うことに疑問を感じたり、自戒の念を抱いたりしてきました。

----もっと違うこと、とは?
 取材の仕方に関して、だれにも偏見をもって取材してはいけないと痛感したんです。 取材の仕方に関して、だれにも偏見をもって取材してはいけないと痛感したんです。
たとえば、私自身、ニュース番組の街頭インタビューで、始めから「こういう意見がほしいから、こういう人に聞こう」とマイクを向け、自分の思ったとおりの意見を聞き出そうとして、必死に質問を重ねることがよくありました。
ですが、インタビューを受けてくださる方は、そんな私に絶対に本音を語ってはくださいません。「心に響く一言」は絶対に引き出せないのです。
----そういえば、いろいろなテレビの街頭インタビューなどに、「おばちゃん」らしい意見、「おっちゃん」らしい意見を期待してこの人に聞いたのか、「女性」っぽい意見、「男性」っぽい意見を期待してこの人に聞いたのか、などと思えるシーンが時々あり、「予定調和」を感じると見る側もしらけます。
番組のつくり方も、同様です。
近ごろは、メディア全体として、多くの番組が女性に喜んでもらえる内容にしよう、情報番組は「若い女性」と「主婦」をターゲットにしよう、という流れになってきています。活発にまちを歩いているのも、購買力を持っているのも女性ですから、自然な流れとしてそこまではいいんです。だけど、それが「女性がターゲットだから、易しく、分かりやすく、噛みくだいた番組にしよう」となってしまうのは、良いとはいえないですよね。
また、私自身、テレビ番組を見ていて、「できるだけ易しい内容にしよう」「大きな字幕や効果音を使おう」「プチプチと切って編集し、『引き』のある見せ方をしよう」といった流れを感じて疑問に思うことがあります。
----「女性に好まれるためには、易しい番組であらねば」と思っている制作者の多くは男性?
先にも言ったように社員の男女比率の構成上、男性が多いですが、実際の男女の差ではないでしょうね。男性目線に疑問をもつ女性もいれば男性もいる。放送局の全員が疑問を持っているかといえば、そうでないということでしょう。
----「ニュースワイドショー」的な番組のコメンテーターにやたらタレントが多いのも、気になります。
だれにも難しい国際政治や医療の話の時などに、分かりやすくさせるため、専門家に率直に質問する「視聴者代表」としてタレントを登場させる形は確かに増えています。
一般のニュースのコメンテーターにもタレントの採用が増えてきているのは、「視聴者はこの程度のものを好むのだろう」といった制作側の考えの表れかもしれません。そこには勝手な思い込みや偏見がないか、発信する側は常に考えていかなければならないと思います。
|


