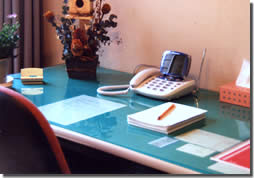 |
| ひょうご被害者支援センターへの電話相談はここで受けられる |
被害者が支援者になることを垣添さんはこう言う。
「2つあります。まず、遺族はトラウマを抱え、自らの癒しをしなきゃいけない人。そういう人に他人の面倒を見てほしいとは本来、言うべきことじゃない。それはさらに被害者を落ち込ませることになるので、あくまでも被害者の自発性、自主性が基本原則。そういう意味では、ある程度、立ち直りできつつある人でなければ無理といえます。その一方で、犯罪が家族に起きても、しっかりした支援があって立ち直れた被害者は、自ら得た体験をまた別の遺族に与えることができる。いわば拡大再生産していって、次の支援の大きな力になれるんです。さらに、被害者として自分はどういう支援がしてほしかったか、何が不足していたか、支援のプログラムの必要性も具体的に、実践的につかめる。しかも、新しい被害者に接する時に、もっとも被害感情を共有しあえる存在になりうるのです」
誰もが高松さんのように、大きな心の傷を負って裁判もかかえながら、他の人を支援していくという取り組みができるわけではない。
「遺族の方は、まずしっかりした自助グループをつくって心の傷を癒し、立ち直りをして、その人たちの要求が、国や社会で実現できるようなプレッシャーグループとして発展もらう必要がある。兵庫の場合は、たまたまそういう方がいらっしゃっただけ。そういう人たちに依拠して民間の支援団体の主要メンバーに入れることが、組織的、理論的にいいかどうかは、これから吟味していかなきゃいけない問題です」
罪を憎んで、人を憎まず?
2000年の犯罪白書では、犯罪被害者が深い心の傷を長く抱えて生きている実態が明らかにされた。被害者の加害者に対する感情は、「憎い」「かかわりたくない」とするものが多かったとされるが、それも当然だろう。ただ、日本では「罪を憎んで人を憎まず」。加害者の人権を大切とする意識は根強い。公平な立場では、加害者はどうあるべきなのだろうか。
「まず、加害者は被害者としっかり向き合うこと。そのなかで真摯な理解、認識をして、慰謝し、責任を感じていくべきです」と語る垣添さん。
「特に少年法では、遺族の傍聴もできない中で審判が進められ、また、被害者と加害者を対面させることなく、『自分が犯した罪を忘れなさい』と過去を遮断し、過去よりも新しい人生や未来を考えようという保護主義で進められていく。なぜなら少年は人格も未熟で過渡性に富んでおり、起こした殺人にしても一過性のものであって、その子の人格を決定づけるものではないとされているから。少年側から見ると正しい見方ですが、それでは遺族や被害者のことが、全く考えられていない。被害者の人権も考えた調和のとれた制度にしなくちゃいけないんです」
少年院にも問題があるそうだ。
「審判が下るまでは加害少年の立ち直りに悪影響を与えたり、裁判官の前で心を砕いて語ることをしなくなるからと、被害者とは向き合わせない。しかも、社会復帰のためには自分の犯した行為をしっかりと胸に納め、理解、自覚し、責任を感じ、遺族に対して慰謝慰藉をし、建設的行為をするための動機づけをしていかなければいけないのに、少年院では指導理念として共生という観点が欠落していて全くなされていない。飯を食えるように職業訓練をしたり、勉強はしっかりやるが、自分の罪について遺族と向き合い、遺族の声を聞き、その中で何かをつかみ、考え、自分の罪の内容を理解し、同時に保護者もそこで共に反省し、遺族と交流して社会復帰していくことが必要だと思うのですが、まだまだできていなのが現実です」
被害者は、加害者への厳罰だけを願っているのではない。人が人らしくあるために、被害者の権利を認め、支援制度の確立を求めているのである。
 垣添さんは、5年前のことが今も忘れられないという。
垣添さんは、5年前のことが今も忘れられないという。
被害者の気持ちをお金だけで解決しようとする弁護士たちに辟易とした高松さん夫妻が、自分たちの本当の気持ちを理解してもらえる弁護士を探して心身共にヘトヘトになり、垣添さんの事務所を訪れた日のことだ。
「うちの事務所を初めて尋ねて来られた時の高松さん御夫妻は打ちひしがれ、それは悲壮でした。まず、おっしゃったのが弁護士の批判だった。『裁判を起こしたって、加害者からどれだけ金が取れるか』といった話ばかりをするというのです。それは、かつての私自身の姿でもありました」
被害者支援を始めることで別人のように変わっていったという高松さん。
「私にとって、現在の高松さんの元気な姿は夢のようです。その変化に、すごい感動を与えられた。この出会いが、私の今日を支えているといっても過言ではありません」



