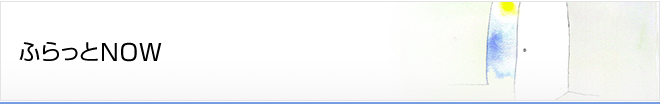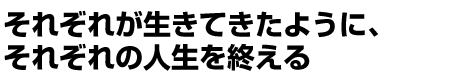高齢者
- 2009/03/02
「人生、終わりあかんでもまあええか」おおらかな看取りを地域でふわっと支援したい。 -
-
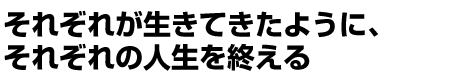
桜井さんが講演などで「もし選べるならどんな死に方がいいか」という質問をすると、ほとんどの人が「心疾患でピンピンコロリといきたい」と突然死をあげる。しかし、その割合はわずか4%ほどで、現実に突然死できる可能性は低く、残された家族にとってもこれほど辛く迷惑な死に方はないという。その一方で、突然死と相反する「住み慣れた家で家族や大切な人に囲まれ眠るように死にたい」と希望する人も多い。
「眠るように死ぬのが大往生なら、突然死は当てはまらない。みんな死に対しての幻想と現実が一致していないんですよ」と桜井さんは笑う。
在宅死には、さまざまなケースがある。
ある日、桜井さんのもとに相談に訪れた一人の女性。「隣町で兄夫婦と同居し、脳梗塞の父親を介護している母親が肺がんと診断され、今後どう支えていけばいいか」という内容だった。肺がんはかなり進み、骨にも転移しているとのこと。女性らは悩んだ末、母親自身に打ち明けたところ、母親は冷静に受け止め、これ以上の手術は受けないで家にいたいと答えた。主治医からも今後の積極的な治療は難しいと伝えられ、在宅ケアを選択。桜井さんは兄宅の近くに住む友人の医師を紹介した。その時、説明したのが「がん末期の痛みを和らげる緩和ケアの技術は進み、往診や訪問看護でコントロールは十分可能だということ」「がんの進行を抑えるような治療と一緒に行うことも可能であること」「万一の場合は入院という選択もあること」だった。それから半年後、母親は家族に看取られ安らかな最期を迎えた。亡くなる1週間前までなんとか父親の食事の介護までしていたそうである。
天涯孤独の団地住まいのおじいさんもいた。最期は家に帰りたいということになったのだが、介護する家族がいない。しかし、元気な頃から団地近辺をすすんで掃除をしたり、近所の子どもたちと遊んだりしていたことで、人気者だったおじいさん。団地の人たちが交代で見守りすることになり、最期まで在宅で看病し看送れたケースだ。自分らしい最期を迎えたのは86歳のばあちゃんだ。阪神大震災の後、洋品店を建て直し、一人で元気に切り盛りしてきた人である。去年の5月、孫が留学する北欧に「冥土の土産や」と行ってきたのだが、どうもその頃から調子が悪かったらしい。しんどいと言う祖母に娘さんは病院に行くように勧めたが、一切検査もせず。ついに年末に倒れ、寝込んでしまった。年明けに診察を受けると、膵臓がんであちこちに転移しており、どうしようもない状態だった。家族は連れて帰りたいと家に戻り、2日後の夜に亡くなった。「見事でした」と桜井さん。多分ばあちゃんは本能的に迎えが近いことが分かった中で、検査をすれば入院となり、海外旅行も店を続けることもできなくなることを察し、北欧行きを決めたのだ、と。現実には、暮れまで店を開き、1カ月後に家族に看取られた。バイオリニストの孫が枕元で演奏する中での旅立ちだったそうだ。
「だが、現実はすべてが上手くいくわけではありません。それぞれの人生の終わり方は、それぞれが生きてきたような経過をたどるんです。もちろん、時にはとんでもない死に方だってある。『おわりあかんでもまあええか、よう頑張ったよね』といった発想も必要です」 - 関連キーワード: