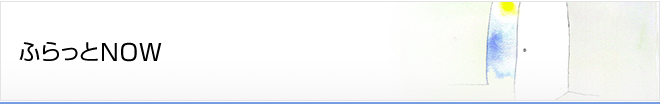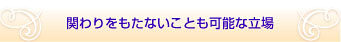
 |
| 「分娩台よ、さようなら」(大野明子著・メディカ出版 2,600円+税)※本の写真をクリックすると、amazonのホームページから本を購入することができます。 |
大野さんが春乃ちゃんを搬送しないことにこだわったのには、大野さん自身の苦い経験も影響している。「周産期センターのような大きな病院では、どんな状況で、どんな子どもが生まれても、すぐに新生児科がみてくれます。子どもはあっという間に私の手の届かないところへ行ってしまうんです」。たとえば「お子さんはダウン症です」と両親に話すのは新生児科の医師であり、その後の関わりももたなくてすむ。「出生後の関わりをもたないことも可能で、実際の生活も見ないので、思いをはせることもあまりないのです」。
関わりが少なければ、葛藤や心の痛みにとらわれることもまた少ない。しかしそれは、自分の判断や思いを現場で生かせないということでもある。大野さんもまた、自分の思いとは裏腹の医療が目の前で行なわれるという経験を何度もした。たとえば、大学病院での当直の夜、救急車で運び込まれてきた妊娠中の若い母親がいた。痙攣発作を起こしているというのに、あちこちの病院から受け入れを拒まれ、たらい回しの状態だった。とにかく検査してみると、悪性の脳腫瘍の疑いが強い。「けれど、私は一晩だけの主治医。朝になると主治医が決まり、さっさと帝王切開で赤ちゃんを出して、子どもは新生児科へ、おかあさんは脳外科病棟へ移されました。妊娠30週の未熟な赤ちゃんだったので、私は“帝王切開すべきではない、様子を見るべきだ”と思いましたが、そんな“面倒な”選択はされなかったのです」。母親に付き添ってきたのは、若い父親と3歳前後の男の子だった。男の子の手をひき、呆然と立ち尽くしていた父親の姿が目に焼きついている。
どうがんばってみても、医療には限界がある。しかし最も大切なのは、人間が生まれながらにしてもつ力を信じ、命を命として迎えることではないか。自らのお産と母乳育児の体験から、それまでの仕事を投げうってまで産科医を志した原点を取り戻したい。そう考えた大野さんは、勤務医をやめて開業の決意をした。
「今は妊婦さんとの距離が近いぶん、喜びもつらさも一緒に味わいます。主治医は私だけだから関係がしっかり築けて、出産後も検診やOG会を通じて交流がある。そのなかで産科医として、人として、得たものはとても大きいです」と大野さんは話す。

 何の問題もなくスルリと産まれてきたのに、まったく息をしなかった赤ちゃんがいた。生まれる直前まで心音には異常はなく、体のどこにもおかしなところは見当たらなかった。あらゆる手段で蘇生を試みたが、ピクリともしなかった。 何の問題もなくスルリと産まれてきたのに、まったく息をしなかった赤ちゃんがいた。生まれる直前まで心音には異常はなく、体のどこにもおかしなところは見当たらなかった。あらゆる手段で蘇生を試みたが、ピクリともしなかった。
かと思えば、妊娠18週に赤ちゃんを包む胎胞が出てしまったうえに破水し、常識的に考えれば絶体絶命にも関わらず、まるで胎児が子宮口を塞ぐかのような形で動いたためか妊娠が継続し、早産ながら無事に生まれたこともあった。春乃ちゃんのように「障害」があっても、力強い生命力を発揮する子どももいる。そんな時、胎児や新生児の「生きたい」という意志を強く感じる。
こうして産科学の一般常識では説明しきれない出来事をいくつも目の当たりにしてきた大野さんは、どんな障害があったとしても、生まれてきたということ自体がその子の「生きる力」を示していると今は考える。「私は科学教育を受けてきて、産科学も信じていました。産科学が“絶対”だとしていることは絶対に大丈夫だと思っていたんです。けれども命の領域では人間の技術や知識など及ばない部分がどれほど多いか。予防や治療のできない障害を妊娠初期に見つける出生前診断は、どんな理屈をつけても生きる力をもつ命を中絶するという事実は動かせないし、実際に中絶を選ぶ人が多い。選択的中絶なんて体のよい言い方がされていますが、はっきり選別的中絶と言ったほうがよいのではないでしょうか」
|