ふらっとへの手紙 北出新司さん from貝塚 vol.2
2015/05/01

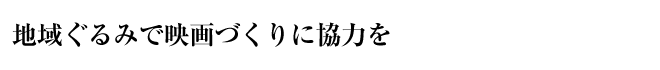
「食肉の仕事と携わる人たちの暮らしを映画にしたい」。纐纈あや監督の申し出を受け入れたぼくたち家族は、地元の支部(部落解放同盟)と、だんじり祭りや盆踊りを取り仕切る町会に出向き、監督に説明をしてもらいながら協力を依頼しました。今でこそ、たとえば祭りから排除するというような露骨な差別はありませんが、地名を出すことでネットで「ここは部落だ」と名指しするなど差別が拡散されたりする恐れがあります。またムラの文化のひとつの象徴でもある祭りや盆踊りを撮影すると当然、子どもたちが映ります。そのことへの配慮などさまざまな確認をして、撮影に入りました。差別を恐れて反対する声がなかったのは、それまでの部落解放運動の取り組みがあったからだと思います。
撮影には1年半かかりました。牛を「割る」場面をはじめ、ぼくたち家族の日常――肉をパックし店頭で販売したり、家族で食卓を囲んだり、年末に一家総出で働いたりと、さまざまな場面が撮影されました。纐纈監督はうちの近くのアパートに部屋を借り、毎日のように通ってきました。最初はカメラが気になって「まだ撮るの」「こんなん撮ってどうするの」といちいち反応していましたが、やがてまったく気にならなくなりました。犬のラッキーまでカメラに慣れたのがおかしかったです。

映画づくりは、ぼくたち家族があらためて「屠畜」の仕事について整理し、考え直す機会ともなりました。映画のなかで弟(昭さん)が話していますが、屠畜をしていると話すと「すごいですね!」と言われます。けれどその肉を食べているのはみなさんです。それは「すごく」ないのでしょうか。「自分たちで育てた牛を食肉にするのに抵抗はありませんか」「かわいそうだと思いませんか」とも聞かれますが、牛小屋を出た瞬間から情ではなく、どれだけいい肉になったかという視点しかありません。「割られる瞬間の牛が涙を流したと本に書いてありました。牛は自分が割られることを自覚するのでしょうか」という質問もよくありますが、ぼくたちにも牛の気持ちはわかりません。自分たちは食肉、屠畜のプロとして、牛を倒す時にはできるだけ苦痛を与えず一発でと思い、その技術と感覚を磨いてきました。それがプロの仕事だと思います。
最初からこうした意識をもっていたわけではありません。親父は小学校で先生からムラの子どもであることで差別され、怒って腕に噛み付いたそうです。それから一切学校に行かなくなったと。ですから文字の読み書きができません。そのことで人にだまされたりバカにされたりすることがあったようです。それでも「読み書きはできなくても一生懸命働いて、子どもたちを育ててきた」という強い自負をもっていました。そうやって自分を支えていたのだと思います。
けれどお酒を飲むと差別への悔しさや怒りが出るようで、よく暴れました。親せきたちも似たようなもので、子どもの頃はお酒を飲んではけんかするという環境がいやでした。荒れた大人たちの根っこに部落差別があることを理解できていなかったので、「いつか出て行ってやる」と思いながら、苦労しながら身を粉にして働く親父の姿に複雑な思いを抱えていました。

そんなぼくが高校で水平社宣言に出会います。高校に入学した1969年は、被差別部落の環境改善と差別解消を目的とした同和対策事業特別措置法が国会で成立した年でした。全国的に被差別部落で解放運動が生まれ、高校生たちも加わりました。ぼくは別のムラから通っていた先輩に水平社宣言を教えられ、そのなかの一文に強い衝撃を受けました。
――ケモノの皮を剥ぐ報酬として、生々しき人間の皮を剥ぎ取られ、ケモノの心臓を裂く代償として、暖かい人間の心臓を引裂れ、そこへ下らない嘲笑の唾まで吐きかけられた呪われの夜の悪夢のうちにも、なお誇り得る人間の血は、涸れずにあった――
「自分のムラとまったく同じだ。これが部落差別なんだ」と一気に理解しました。このことが大きな契機となり、ぼくも地域で活動をはじめると同時に家業を継ぐ決意を固めました。(2015年4月談)

