誰も取り残さない社会をめざして ひるむことなく進みたい DPI日本会議 尾上浩二さん
2016/11/03

2016年7月26日、相模原市の障害者施設で、19名が殺され、26名が負傷するという事件が起こった。容疑者として逮捕されたのは、その施設の元職員だった。なぜ、このような事件が起きたのか。事件の「本質」は何か。そして再発防止のために何が必要なのか----。 認定NPO法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議で副議長を務める尾上浩二さんに話をうかがった。
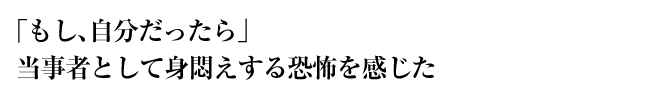
――最初に事件を知った時、どんなことを思われましたか?
身悶えするような恐怖とは、こういうものかと思いました。というのは、私自身、生まれた時から脳性まひの障害があり、子ども時代は入所施設で暮らしていたからです。当時は、「障害を克服する」という名目であれば何をしてもいいような時代状況でした。私の場合、腰の曲がりを矯正するという名目で、就寝時もベッドに体を固定された状態で寝ていたんですね。縛られた状態で、夜の6時半から翌朝6時までの間、ずっとです。そんな体験があるので、もし当時の自分が寝ている間に包丁を振りかざしてきたらどうなっていただろうと、想像せずにはいられませんでした。抵抗どころか、身動きもできない状態ですから、どうしようもなかったでしょう。そう思うと、本当に恐ろしいです。
この事件の3ヶ月前に、障害者差別解消法が施行されました。生きる権利を奪われてきた障害者が声を挙げ続け、30年40年の運動の末、ようやくできた法律です。決して十分な内容ではありませんが、それでも何とかここまできたと思っていただけに、全身の力が抜ける思いもありました。
――容疑者が逮捕された後、事件を起こす前の言動がさまざまに報道されました。そのことについてはどう受け止められましたか?
一斉に報道が始まった2日目ぐらいから、容疑者に措置入院歴があったということがクローズアップされた形で報じられるようになりました。厚生労働大臣が記者会見で「措置入院制度のあり方を見直す」という発言をしたのが、ひとつのきっかけになったように思います。
そして実際に今回の事件を受けての対策検討会議を発足させました。テーマは「施設の安全対策の強化」と「措置入院制度の見直し」です。しかし、私はこうした流れに強い危惧を抱いています。それは、今回の事件が「平穏な暮らしをしていた知的障害者を、精神障害者が殺めた特異な事件」として矮小化されては、事件の本質や本当の意味での再発防止につながらないと考えるからです。
――事件の本質とは何でしょうか。
直裁に言えば、今回19名の方が一度に殺害されたというのは、そこにそれだけの人が集められた状態にあったということなんですね。別々に住んでいれば、それぞれの部屋を渡り歩いている間に逮捕されたでしょう。つまり、事件の現場となった施設にかぎらず、社会的な歴史のなかでつくられてきた、障害者の隔離の歴史----障害者を社会から隔離したところに住まわせるという問題点が集中的に現れたと言えるのではないでしょうか。
今回の事件を受けて、さまざまな媒体から取材の申し込みがあり、少なからぬ記者から「知的障害者の人権と精神障害者の人権を両立させるのは難しいですね」と言われました。「平穏に暮らしていた知的障害者の暮らしや命を、精神障害者がめちゃめちゃにした」という、決めつけに近い思い込みを感じました。それは違うということをしっかり押さえていかなければと強く感じています。
ところが、自分の子ども時代の施設体験を取材でお話しすると、「寝ている時にも縛られているって、どういうことですか?」といった感じで、なかなか話が通じないのです。ひとつひとつ解きほぐすように説明して、何とか理解してもらいました。あらためて、それだけ障害者施設といわれる場所の状況が、まだまだ社会には知られていないんだなと思います。
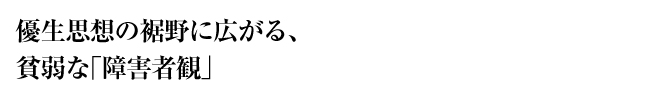

――事件そのものにも衝撃を受けましたが、容疑者が事件前、衆議院議長にあてて書いたという手紙の内容も衝撃的でした。
私に取材を依頼してきた記者のなかには、尊厳死や出生前診断といった問題にずっと取り組んできた人たちもいました。その人たちは手紙の内容があきらかになった時、「この事件は優生思想の問題だ」と察知したようです。そして、容疑者の言動や手紙の内容が繰り返しテレビなどで流されることに、「これでは二次被害を生み出しかねない」という危機感を抱いていました。しかし、そう考える記者は一部で、多くの報道関係者は「(容疑者は)ナチスに感化された」「1940年代の古い考えに影響を受けた容疑者」という捉え方しかできません。彼が措置入院した際、病院の担当者に「ヒトラーの思想が2週間前に降りてきた」と話していたからです。
確かに優生思想、優生学というものを政策にしたという意味ではナチスのT4作戦(重度障害者の安楽死政策)は有名です。しかしそれは過去の問題ではなく、現在に至るまで連綿と続く問題として捉えなければ、本当の意味で優生思想の問題を捉えたことにはなりません。
T4作戦自体、ヒトラー一人の問題ではありません。その思想を支えた大衆や、積極的に手を貸した精神科医をはじめとする医師たち専門家がいたわけです。そして何より、最初のきっかけは障害のあるわが子に対して「慈悲の死」を望んだ親がいた。その思いに応える形で専門家が手を貸し、T4作戦へとつながっていったのです。
さらに、日本では「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に掲げた優生保護法が1996年まで存在していました。障害者や関係者の粘り強い運動によってようやく廃止されましたが、被害者に対する謝罪・補償を政府は未だにおこなっていません。
容疑者自身がなぜああした行為に及ぶまでの思考を形成し、実行にまで至ったのかということは個別具体的に解明されなければならないと思います。ただ、私自身はここ数年、社会が非常に不寛容になっていることと切り離しては考えられないなと感じています。障害者や高齢者、生活保護を受給している人など何らかの支援が必要な人たちに対して排除するような動きがあります。政治家や作家といった力のある人が堂々と、高齢者に対して「何歳まで生きるつもりだ」などと言いますよね。以前なら社会的に大問題になっていたような発言なのに、最近は許容するような空気を感じます。こうした社会的素地のうえに今回の事件があると私は考えます。
――容疑者が書いた手紙から、尾上さん自身は何を読み取られましたか?
事件後の取材で、彼が特別支援学校の先生になりたいと考えていたこと、それが叶わなかったので「障害者の役に立てれば」ということで施設の職員になったという経緯があきらかになりました。ところが彼は手紙のなかで「障害者は人間としてではなく、動物として生活しています」「障害者は不幸を作ることしかできません」などと書いています。これはとても貧弱な障害者観だと思います。
でも悲しいかな、事件が起きた施設に限らず、入所施設では「集団処遇」という対応がなされているのも事実です。多数の障害者に対して1人、2人という職員が、限られた時間のなかで食事や介護、着替えなどをするのです。どうしても流れ作業的になり、1人1人とていねいにコミュニケーションをとる余裕がありません。うがった考え方かもしれませんが、そうした状況のなかで、「障害者の役に立ちたい」と思って関わったけれども、たとえば「感謝の言葉」も返ってこない、行動障害がある人がパニックになったといったことが続いたとしたら、「報われない」という感情が生まれ、「障害者は不幸しかつくり出さない」という貧弱な障害者観へとつながっていったのではないかということです。哀れみの対象である障害者のために「援助してやったのに」、感謝というレスポンスが返ってこなかった。そこで「裏切られた」という怒りや不満が生まれても不思議ではありません。
優生思想とは、命を「生きるに値する命と、値しない命」とに切り分ける考え方です。障害者を生きるに値しない命と決めつけ、殺害にいたったというのはあきらかに優生思想です。優生思想が山のてっぺんにあるとしたら、その裾野に貧弱な障害者観があります。それがなぜ形成されたのかが非常に気になるし、実はそのことと、長年の隔離政策は無縁ではないと感じています。
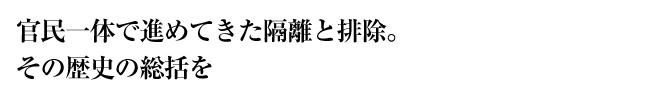

――「生きるに値する命」とは、たとえば働いて納税したり、子どもを産み育てたりする人の命でしょうか。結局は命が経済の問題にされていると感じます。
社会にとって役に立つか立たないかという功利主義的な発想があると思います。私も子ども時代から「障害のある人間にとっての人生の目的とは、障害を克服することだ」と言われ続けてきました。そして障害を克服するためには、多少痛みや苦しみがあっても耐えて、努力すべきだと。障害を乗り越えてこそ、初めて意味のある人生になるのだと。
「障害は克服すべきものだ」という考え方と、「障害はあってはならない」という考え方の間にはさほど大きな断絶はないと思います。
生まれる前にできるだけ「不良」な子孫の出生を防止しようということで優生保護法がつくられ、不妊手術や人工中絶がおこなわれてきました。兵庫県では1966年から1975年まで「不幸な子どもの生まれない県民運動」を行政と住民が一体となって推進していました。「障害のある子は不幸な子で、その家庭も不幸になる。みんなが不幸になるから、障害のある子どもが生まれないようにしましょう」ということです。同じ発想で、ハンセン病では「無らい県運動」がありました。行政が強権的に患者を隔離するだけではなく、住民が密告するのと連動するような形で進められました。
こうしたことは間違っていたし、「殺されていい命」も「死んでもいい命」も「生まれてこないほうがいい命」もないということを社会全体でしっかりと共有していくことが必要です。そのためにも、まずは歴史に真正面から向き合って検証し、総括することが大事です。しかしそれがまったくなされていません。
長年の障害当事者の運動の結果、バリアフリーや地域で暮らすためのホームヘルプ、在宅サービスなどはある程度充実してきました。しかし、新しいことをしながら古い部分も温存しているという感じがあります。これまでの歴史や政策を総括し、問題点を踏まえたうえで「新しいこと」へと転換していかなければ、差別意識や優生思想は解消できないでしょう。
実際、まだ多くの人が入所施設で暮らしています。また、分離教育、特に特別支援学校に進学する子どもが増えています。
――私たちはこれからどんな社会を目指していけばいいのでしょうか。
私が副議長を務める、認定NPO法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議では、事件の翌日に声明を出しました。ひとつは、この事件が優生思想に基づく行為であり、それを生み出した社会状況は許されるものではないということをはっきりと言うこと。そしてもうひとつは、これからも私たちはひるむことなく、共生社会を引き続き求めていかなくてはならないという決意表明です。
21世紀に入ってから、国や大阪府が地域移行計画を立てるなどして、地域移行を進めてきているのは確かです。しかし中軽度程度の、いわば厚い支援がなくても生活できる人が中心で、重度障害や重複障害のある人、あるいは長年施設で暮らして高齢になった人が地域で暮らすことにはなかなか展望がもてない状況になっています。こうした「誰かを取り残す地域移行」が、入所施設の問題を非常に厳しい状況に追いやってしまったのではないかと感じています。
私たちDPI日本会議は、あらためて「誰も取り残さない地域移行」に向けて進むべきだと考えています。誰かを取り残してしまえば、「この人たちに生きる意味があるのか」という偏見を温存・強化させてしまう可能性があるからです。
さらに、再発防止という意味では、社会から優生思想をどう取り除くかという大きな課題があります。まずはこれまでの歴史の総括。そして「殺されていい命などない」というメッセージを共有化していくこと。そのための実践のひとつとして、分離教育をインクルーシブなものにしていく。同時にどんな重度の障害があっても、地域で暮らしているというのが当たり前の状態をつくっていく。「誰も取り残さない」地域移行が可能になるよう、しっかりと社会が支援していく。こうした取り組みこそが再発防止への道です。安全対策という名目で施設を囲う壁を高くしたり、措置入院の見直しという名目で精神障害のある人を再び隔離の方向へもっていけば、「障害者のいない世界をつくる」と容疑者が掲げた目的に沿った社会に突き進んでいくことになります。それはすべての人にとって幸せな世界ではないはずです。
●DPI日本会議
「相模原市障害者殺傷事件に対する抗議声明」
(2016年9月/取材・構成/社納葉子)

