ジェンダー
- 2007/10/18
改正雇用機会均等法について知ろう! -
-

セクハラ防止への事業主の措置義務の追加 
これまでの法律では、「事業主は、女性労働者に対してセクハラが行われないよう、雇用管理上必要な配慮を行うこと」が義務づけられていたに過ぎなかったが、改正法では、「女性労働者」という文言が「労働者」に変わり、「男性労働者」も対象に含められるようになり、適切に対応するための体制の整備を義務づけられると共に、是正指導に応じない場合は企業名公表の対象となった。「セクハラは、男性が女性に向けるハラスメントだというイメージがありますが、男性から男性、女性から女性への同性間でも、また女性が男性に向けても、性的な不快感を覚えるものすべてが対象になったのは、大きな前進です」
たとえば-----。
男性間でよく聞くのは、新入社員が宴席で上司から「裸踊りをやれ」と強いられるケース。同僚に買春に誘われ、断ると仲間はずれにされるケース。性的経験がないことをからからかわれるケースなど。
女性上司が、男性にしろ女性にしろ部下に、結婚や子育てなど家庭内のことを根掘り葉掘り聞くケースも、場合によってセクハラに該当する。上司は心配して聞いてあげているつもりでも、部下は継続してしつこく聞かれることにより不快感を感じ、仕事に身が入らなくなくなることもあるわけだ。セクハラへの対応が「努力義務」となった99年の改正法施行以降、すでに大企業はセクハラ相談窓口の設置や、外部の相談機関との連携などをしてきているが、今回の改正で「措置義務」となり、中小企業も含め、法人格の有無に関わらずすべての事業主に、次の項目が「義務」となった。
・職場におけるセクハラの内容およびセクハラがあってはならないことを就業規則・服務規程に懲戒規定を明確化し、労働者に周知・啓発すること
・セクハラ相談窓口(外部委託可)を設け、相談に迅速かつ適切に対応すること
・セクハラの事実確認ができた場合、加害者・被害者への措置を適正に行い、再発防止に向けた措置をとること
・セクハラ相談をした労働者に、その相談をしたことを理由に、不利益な取り扱いをしてはいけないこと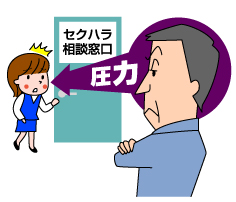 Q14「当社は、人間関係に問題がなく、セクハラ問題が起きたことがありません。それでも、就業規則にセクハラ規定を設けたり、窓口を設置したりしなければなりませんか?」(旅行関係)
Q14「当社は、人間関係に問題がなく、セクハラ問題が起きたことがありません。それでも、就業規則にセクハラ規定を設けたり、窓口を設置したりしなければなりませんか?」(旅行関係)Q15「当社は、相談窓口を以前から設けてきましたが、実際に相談は一件もありません。セクハラが起きていないということだと思うのですが・・」(広告関係)
これらの発言に、松井さんは「認識が甘い。ハラスメントが起きていない、あるいは、今後起きないということはあり得ない」ときっぱり。セクハラの声が上がらないこと(Q14)、相談がないこと(Q15)こそ問題で、「相談窓口が機能していない状況かもしれない。力関係の中で弱者が口をふさがなくてはならない実態」を認識しなければならないという。
「相談窓口は、相談者を待っているだけでなく、調査アンケートをとるなど積極的に、すべての社員にアプローチするべきです」
実際、「相談がない」と言っていた事業所がアンケートをとると、「これがセクハラにあたるかどうか分からないが」といった例から、「実はずっと我慢してきた」「これまで諦めてきた」といった例まであがり、セクハラの実態が浮かび上がったケースもある。また、相談担当者がセクハラ問題解決に向けての訓練を受けているかどうかも大いに問題だ。Q16「以前、友人がセクハラ被害を受け、社内の窓口に相談しましたが、最終的に彼女は会社にいづらくなって退職に追い込まれました。加害者の上司は、部署替えがあったものの、のうのうと会社に残っていて、やりきれないのですが・・」(流通関係)
これは、まさに「セクハラ相談をした労働者が、結果的に不利益な取り扱いを受けた」典型だ。少なくないというこういったケースを是正するために、「すべての人権侵害は許しません」という方針をすべての事業所は明確にし、周知徹底させるべき。明確にしていないなら、労働者が会社に明確にするよう会社に働きかけるべきだろう。社外の相談窓口の電話番号を書いた紙を貼るだけでも、前進すると松井さんは言う。
- 関連キーワード:

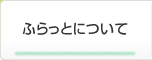
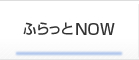



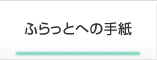


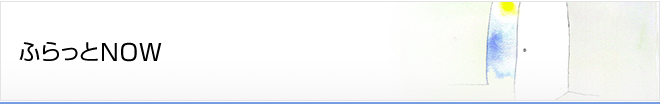
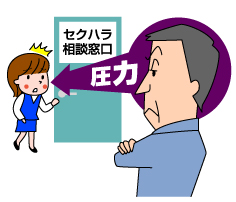 Q14「当社は、人間関係に問題がなく、セクハラ問題が起きたことがありません。それでも、就業規則にセクハラ規定を設けたり、窓口を設置したりしなければなりませんか?」(旅行関係)
Q14「当社は、人間関係に問題がなく、セクハラ問題が起きたことがありません。それでも、就業規則にセクハラ規定を設けたり、窓口を設置したりしなければなりませんか?」(旅行関係)