一人ひとりの言葉と生きる力に心を寄せて 琉球大学教授 上間陽子さん
2017/08/02

上間陽子さんは、大学で教えるかたわら、性風俗で働く若い女性たちの聞き取り調査やサポート活動をしている。調査で出会った女性たちとの関わりをまとめた著書『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』は、大きな反響を呼んだ。彼女たちの語りや生活から浮かび上がってきたものは何か。彼女たちが抱える「生きづらさ」とは何か。そして上間さんは、彼女たちとどう向き合っているのか----。
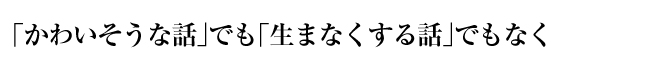
| 『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』は2012年の夏から沖縄ではじめた調査をきっかけに出会った女性たちのうち、キャバクラで勤務していた、あるいは「援助交際」をしながら生活をしていた、10代から20代の若い女性たちの記録である。調査はもともと、風俗業界で働く女性たちの仕事の熟達の過程、生活全体、そして幼少のころからの出来事に注目した聞き取り調査として行われた。しかしそこで語られた内容は、上間さんたち調査チームが予想していたよりもはるかにしんどいものだったという。(同書「あとがき」より) |
――『裸足で逃げる』は、これまでにあまりなかった本だと思います。上間さんは研究者でありながら分析的でないのが印象的でした。彼女たちと同じ時間を過ごし、フラットな立ち位置で「うんうん」と話を聴く姿が立ち上ってくるようで。反響はいかがですか。
びっくりするぐらい、いろいろな方から反応がありました。本では10代の人の話を中心にしたのですが、NPOなど民間で子どもの支援活動をしている人や性暴力に関わっておられる医療関係者、弁護士さん・・・。わざわざお手紙をいただいたりして、たくさんの方が真摯に活動していらっしゃるんだなあと。
――DVや経済的困窮、親との関係など自分自身が生きていくだけで大変な環境にいるなか、10代で妊娠、出産する女性たちも少なくないですね。
確かに若年出産は危うさをはらんでいるんですけど、サポートがたくさんあれば、「母になっていく」んですよね。誰にとっても「母」業をやるのは難しいことで、サポートは不可欠です。それが足りないなら、やればいいだけのこと。何かに依存しないと生きていけない子どものそばにいて、しかも本人がまだいろんなものを抱えている。それに対して何かするのは、善意でも情熱でもなく、社会がやらないといけない。原稿を書きながら、そんなことをすごく考えていました。同時に「こんなに大変なんだから、若年出産させるな」という話には絶対したくないと思っています。
反響のなかでストレスを感じるのは、「こんなかわいそうな子たちがいる社会を改良しなくちゃいけない」という捉え方です。再分配の議論は絶対に必要だと思っています。でも、「かわいそうな子」という捉え方は、自分を安全圏に置いている言葉ですし、それを基軸に生まさない社会をつくることが「社会改良」だとは思いません。彼女たちが大変なのは事実です。でも彼女たちなりに、なんとかよくしようと思って生きてるんですよね。そして何らかの偶然やいろんな組み合わせのなかで、危うくなく育てている人たちもいます。つまり、生まれた子どもたちをいかに育てていくかの議論が必要であって、行政はそこを徹底するのが仕事だと思います。生まなくする話ではないということは、何度でも押さえておきたいです。
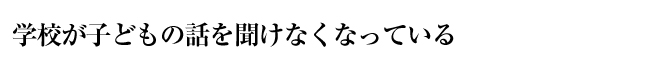
――個人がよりよく生きたいと思って選んだことが、社会的には「かわいそう」「大変」と捉えられてしまう。一人ひとりの選択や人生と、社会の問題として取り組むべきことを切り離して考えないと。何より「かわいそうな子」と決めつけるのは違いますよね。
はい。そこは腑分けしながら議論してもらわないと困るなと思っています。本を書いた大きな目的のひとつは、学校現場にこの現状を突きつけることでした。たくさんの少女と出会ってきましたが、彼女たち、本当に話を聴いてもらっていないんです。
たとえば本にも登場する春菜さん(仮名)という少女は、15歳で家を出て4年間、民宿で暮らし、「援助交際」でお金を稼ぐ生活をしていました。家を出るに至るまで、親の離婚や再婚などで目まぐるしく生活環境が変わっています。父親や「マーマー」と呼ぶ新しい母親、きょうだいとの幸せな生活もありました。でも結局、父親の暴力が元で離婚、3人のきょうだいはバラバラになってしまいます。小学生だった春菜さんは、寂しがる妹のために、毎日、学校が終わるとバスに乗ってマーマーと妹が暮らす家に通ったそうです。そして夕方になると、またバスに乗って、誰もいなくなった家に一人で帰っていたと。
中学生になる頃、父親に新しい恋人ができて一緒に暮らし始めました。ところが父親が単身で東京に出稼ぎに行くことを決めてしまう。春菜さんは知らない女性と2人で、かつてにぎやかに楽しく暮らしていた家で暮らすことになりました。それがきっかけで父親との仲も険悪になります。そのことを「ほんっとにあの時が人生最悪」という言葉で、どう最悪だったのかと表現するんですね。そういうふうに俯瞰して言語化できることはすごいと思うし、幸せに暮らしていたお家で知らない女の人が来て暮らすことになったら本当にいやだったろうとお話を聞いて納得しました。でも春菜さんが20歳になるまで、彼女の話を聞いた大人は誰もいなかったんです。当時の先生たちに文句のひとつも言いに行きたい気持ちですが、春菜さんは担任の名前も誰ひとり思い出せません。周りにいたはずの大人たちは、なんで誰も気付かなかったんだろうと思います。学校がこのままでいいはずがない。けれど、むしろ学校に対する締め付けは厳しくなるばかりで、危機感を抱いています。
――どんな締め付けですか?
2007年から全国学力・学習状況調査が始まっていて、沖縄はずっと最下位でした。ドリル学習を徹底的にやることで、点数は上がってきましたが、ついていけない子どもたちが結果的に学校から排除されていく空気が生まれています。しんどい状況にある子どもたちは、もともと排除されることに対してとても敏感です。
しんどい子がいるとなると、すぐ「スクールソーシャルワーカーを増強します」という話になり、実際沖縄の貧困施策では、スクールソーシャルワーカーや寄り添い支援員の増強が言われています。でも子どもは日常生活を共有して、「あ、この人なら聴いてくれるかな」と思った時、ふと話し始めたりするもの。そういう場所をつくることなくして、あるいは日常的に子どものそばに立っている人なくして、子どもが語るわけがないと私は思っているんですね。
だから、今、学校の先生たちが子どものそばにいられない、あるいはそばにいたいと思っている先生ほど苦悩している状態に対して、とても腹立たしく思っています。

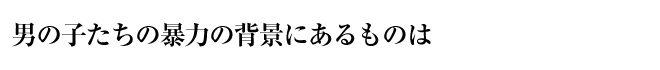
――本に登場する人たちすべてに、暴力も大きく関わっていますね。父親、兄、恋人・・・「援助交際」や風俗店に来る客からの暴力もありますが、本来なら安心できるはずの関係性のなかにもすさまじい暴力があります。
調査をしていると、沖縄では男の子たちの暴力が半端でないことをあらためて感じます。ある事件を起こしてしまった少年が「先輩たちの暴行が怖かった」と供述していました。だいたい中学校時代のネットワークなんですが、肋骨を折られたり海に沈められたり・・・。危ないところにいる男の子たちが暴力の使い手になります。
ただ、それがなぜ許されているのかという時、軍隊の力はやっぱりあると思っており、それはこの本を書いた動機でもあります。沖縄では「外人」をすごくかっこいい存在とする風潮があります。その「外人」のマッチョリズムが男の子たちにとってはとても近しい文化なんですよね。暴力をどうするのかということにも学校は向き合わなければと思います。暴力の発動は、惨めさであったり、自分が毀損された体験であったりすると思います。男の子たちもそれが語れないまま、暴力に吸い寄せられていく。彼らが力を得た時に、最も弱いところに暴力を行使してしまうことに対してどうするのか。沖縄に軍隊がこれほど集中していることに対しては、これでいいのかと日本人に問いたいですし、そして彼ら自身は、自分のことを語る体験を持たなくてはならないと思います。惨めさや弱さについて語ることは、暴力を制御するためには不可欠で、公教育である学校が担うべきだと考えています。

――沖縄をはじめ、子どもたちをめぐる状況に危機意識をもち、「支援」に関わろうとする人たちがいるわけですが、「支援」について上間さんはどんな考えや思いがありますか?
「支援」という言い方、便利なので使っちゃうんですけど、すごく優しい、サポーティブなイメージがあるので違和感があります。私はけっこう必要なことについてはドライに話をするので。
たとえば大人は子どもに対して、道徳的、感情的な部分を発動しがちですが、それだけでは子どもたちに響かないと思ってるんですね。「好きでもない人とセックスするのはよくない」と言っても、現実問題として風俗で稼ぐことで家族の生活を支えたりしているわけなので。それよりも、メリット/デメリットという観点でちゃんと話せたほうがいい。STD(性感染症)の知識や罹らないようにするための工夫、地域の店で働くことのリスクなど具体的なことを話し合います。「親には絶対に知られたくない」と言う未成年にも、「もしSTDに感染していたら保険証を使わないといけないし、隠し通すのは難しい」と最初にはっきりと伝えます。
----何もかも受容するのでもなく、指導や説教をするのでもなく、今あるリスクをより回避するために何ができるかを話し合う。今、必要なことを一緒に考える。テクニカルな話をすることが逆に「話しやすい」「聞きやすい」のかもしれませんね。
テクニカルって、いい言い方ですね。「なるほどねー」「すごいねー」と話を一生懸命聞くだけで、その子自身が、自分がどうしたいかをわかり、どうにかできる事態もあります。でもどうにもできない事態もやっぱりあるので、そういう時にはテクニカルに進めたほうがいいですね。
――その人の生活や人生に入り込んでしまうことも少なくないわけですが、「ゴール」はイメージされているんですか?
ゴールはありませんが、何らかのコミュニティに渡せたらいいなと思います。当事者同士で話せる場所であったり、当事者でなくても「ここにいると何となくラクチン」みたいな場所が1カ所でも2カ所でもあれば。なかなか難しいですけど。調査5年目を迎えて、自力で作り出した方もいらっしゃいますし、やはり難しい方もいます。
ただ、私は自分の仕事を、「支援者」じゃなくて「調査屋」だと思っています。話をちゃんと聞いて、どういう世界に生きているのか、何がその人の世界の見え方なのかみたいなことを聞いて、社会に伝える仕事が第一義的にはあると。そしてこの仕事がすごく好きなんですよね。そのなかで必要なことが出てきたので一緒に動きましょうという感じ。だから「支援」をしたいわけじゃないんです。もちろん必要なことがあれば一緒に動きます。そのうえで、これからも「あなたを見てるよ」「話を聞いてるよ」という立場でいたいと思います。
――ありがとうございました。
(2017年6月インタビュー 取材・構成/社納葉子)
『裸足で逃げる 沖縄の夜の街の少女たち』
沖縄の女性たちが暴力を受け、そこから逃げて、自分の居場所をつくりあげていくまでの記録。
1,700円+税 太田出版


