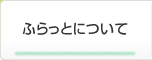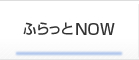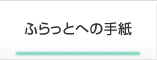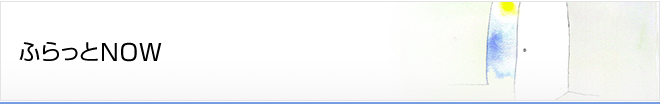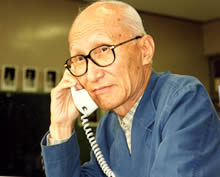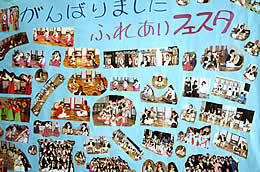多民族共生
- 2002/09/19
李仁夏さん(社会福祉法人青丘社理事長) 共生は多様な文化を認め合うことから始まる -
-
「同化」から「共生」へ
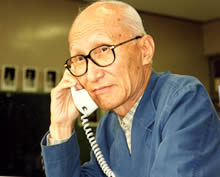
李さんたちの地道で着実な活動は、1974年に社会福祉法人青丘社として認可を受けるという形でひとつの実を結んだ。さらに、1982年には青丘社の要望により桜本地区に子どものためのコミュニティスペース「子ども文化センター」と日本人と在日韓国・朝鮮人とがふれあい、交流できる場とを兼ねた「ふれあい館」を建設し、その運営を市から委託されることになる。
この時、地域で反対運動が起きた。「公共施設をなぜ朝鮮人に任せるのか」「逆差別ではないのか」という反対意見に対し、粘り強い、しかし一歩も引かないという強い意志で話し合いを重ねた末、1988年のオープンにこぎつけた。オープニングのセレモニーで真新しい鍵を手にした理事長はこう言った。「この鍵は、ふれあい館の扉を閉めるためではなく、誰にでも開かれるための鍵として使わせていただきます」
「2年後に地域の町内会長さんたちを招待して記念パーティーをしました。その席でひとりの会長がポロッと言ったんです。“こんなステキなふれあい館を、なんでしゃかりきになって反対したんでしょう”と。ようやく僕らの前で本音を言える関係になったんですね。敵意を友情関係につなげる。それを目指していただけに、ほんとうに嬉しい言葉でした」と李さんは話す。そして「要求」から「参加」へ
地域に根ざした活動をする一方で、李さんたちは法律上での民族差別撤廃に向けての運動も進めていく。1974年、在日外国人には支給されていなかった児童手当を要求することから始まり、就学案内の要求、要保護世帯の奨学金制度問題などに取り組んだ。
これに対して川崎市は国に先駆けて国民健康保険制度の国籍要件を外し、1975年には外国籍をもつ人の市営住宅入居を認め、市の財源から児童手当の支給に踏み切るなど、数々の先進的な施策を打ち出し、全国の自治体に大きな影響を与えたのである。
こうした一連の動きのなかで、外国人の地方参政権を要求する声が高まってきたのは自然な流れだったといえるだろう。李さんたちは「要求から参加へ」を合言葉に働きかけを続け、その結果1994年に国に向けた定住外国人の地方参政権の意見書が川崎市議会で採択され、さらに1996年、全国に先駆けて「川崎市外国人市民代表者会議」が発足した。外国籍をもつ住民が市長任命の諮問機関のメンバーとしてさまざまな提言をし、市条例によって独自性・独立性(調査権)を保障されるという、それまで事実上は一市民でありながら行政にはまったく関わることができなかった在日外国人にとって、そして行政側にとっても画期的なことである。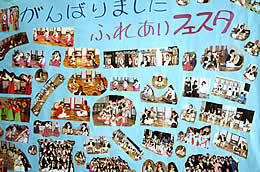
「ふれあい館」にはさまざまな文化を持つ子どもが集まってくる 代表者になる条件は、外国人登録を行っている満18歳以上で、市内に1年以上居住し、会議に必要な日本語能力があることで、推薦と公募者のなかから国別の構成比率によって選任される。一定の日本語能力が認められているとはいえ、言葉に対する理解や表現力にはやはりばらつきがある。また、何十年と日本に住み、あるいは日本で生まれ育った人と、ニューカマーと呼ばれる滞日歴が数年の人たちとの間に対話やコンセンサスが成り立つのかを危惧する声もある。しかしボランテイィア通訳の同席が認められたり、すべての資料や議事録にルビが付くなどきめ細かな対応と、共通の問題意識の上に成り立つ連帯感や共感によって、コミュニケーション不全は今のところ起きていない。
「共生」が日本の社会を豊かにする
「会議」は2002年度で第4期を迎えた。李さんは1期と2期の委員長に選ばれ、この新しい取試みの基礎を築くのに大きな役割を果たした。6年の間にはさまざまな提言が行われ、行政の現場に生かされてきた。なかでも代表的なもののひとつが、入居差別を禁止する住宅条例の制定である。川崎市住宅基本条例に在日外国人の入居保証と居住継続システムからなる居住支援制度が設けられ、協力する意思を表したシンボルマークを店頭に掲示する不動産業者は100店舗を超えた。「共に生きていこう」という思いが端的に表れた事例である。
「川崎市に住む外国人は、1991年に16,397人(市人口総数の1.40%)でしたが、10年後の2000年には20,825人(市人口総数の1.68%)と急増しています。この流れはもはや止められないでしょう。一方で、今でも小学校や中学校では名前の違いからいじめに遭っている子どもたちがいます。これは多様な文化をひとつのものに“同化”させようとすることから起きてくる問題だと思います。“同化”ではなく、虹のようにさまざまな色のまま“共生”することが社会の成熟であり、日本人自身も豊かになることにつながるのではないでしょうか」と李さん。代表者会議には3つのキーワードがある。「要求から参加へ」「個別と普遍」(個別の違いの中から誰をも納得させる普遍的なものを探す)、「相互理解と共生」(外国人を始めとするマイノリティへの理解)。言葉にすれば美しく、誰もが納得する理想である。しかし理想を理想で終わらせないためには、地道で粘り強い活動が必要だ。李さんたちは草の根から始まり、行政を変えながら国に向かってメッセージを発するという市民運動のモデルを実現してきた。その根底には「同化ではなく共生を」という切実な思いが常にあったということを忘れてはならない。
- 12
- 関連キーワード: