偏屈でも、いいかな? 番外編
2007/12/14

「今度の裁判では言いたいこと、言わせてもらうで。また連絡するから…」
2007年3月末に取材した際、別れ際にそう言ったのが最後の言葉になった。飛鳥会事件で逮捕された小西邦彦氏が、同年11月9日、肺がん(新聞発表)で亡くなった。享年74歳。
大阪市内の被差別部落・飛鳥に拠点をおく財団法人飛鳥会の理事長兼部落解放同盟飛鳥支部の支部長だった小西氏は、同会が市有地で経営する駐車場の収益金を横領し、2006年5月に逮捕された。大阪地裁で懲役6年の実刑判決を受け、上告中だった。
一審では罪を全面的に認めて争わなかった。言いたいことを言わせてもらうという冒頭の言葉は、二審では行政や銀行が自分をどのように利用してきたかを法 廷でぶちまける、という意味だった。体調を崩しているという噂は聞いていたが、こんなに早くに逝くとは思わなかった。公判前やインタビュー中も煙草を吸っ ていたので、死因が肺がんというのも意外だった。

私が飛鳥会事件を取材することになったのは、ある新聞で事件の初公判の傍聴記を執筆したのがきっかけだった。事件をより詳しく知るため傍聴し続けた。さま ざまな証言を聞き、事件報道がいかに検察・警察情報に偏っているかをあらためて痛感した。これは事件を起こした本人に話を聞きに行くしかない。そう思い、 連絡をとった。
小西氏にじっくり話を聞くことができたのは計2回、合わせて約5時間ほどである(その一部は『週刊現代』07年2月10日号から3月3日号に4回にわ たって掲載した)。インタビューでは、大阪市の歴代市長や助役、大物政治家、弁護士、運動団体幹部、はたまた許永中、田中森一などといった“ビッグネーム ”まで出て、小西氏の人脈の広さに驚いたものだった。
質問をし終えないうちに話し出すイラチ(せっかち)で、こういうタイプは、えてして人の言うことを聞かないワンマンな人が多い。逮捕要件だった駐車場問 題も、あれはワシがつくったんやから、そこから出た利益もワシのもんや、という理屈だった。そもそも大阪市が市有地を財団法人飛鳥会やなしにワシ個人に貸 しとったら、こんなことにはならなかった、とも語っていた。そんな理屈が通るわけがないのだが、“公”と“私”の使い分けができない人だった。
小西氏は、一貫して一家の長になりたかったように思う。極貧の生活を経て非行少年、さらには極道になるのだが、組をやめ一転して部落解放運動に取り組 む。ヤクザ組織は文字通り“一家”であるが、小西氏はその家長にはなれないと思ったようだ。ヤクザ組織については私に「弱きを助け強きをくじく、なんてウ ソ、ウソ」と語っていた。極道の世界では出世できない、あるいは肌に合わないと思ったのだろう。
劣悪な生活環境にあった飛鳥で、ほどなくして部落解放同盟の支部長になる。生まれは違う部落だったが、第二の故郷となった飛鳥という家の家長になった。 解放運動に否定的な町会派に立ち向かい、部落差別のなんたるかに無知であったムラの人々をまとめ、行政当局と交渉するには、統率力が必要である。小西氏に はその能力があった。だからこそ何十年にもわたって運動団体と財団法人の長を務めることができた。行政や銀行、建設会社、運動団体が実力者の小西氏を頼り にし、各業界や地域のもめごとを収めてきた。
しかしそのことが、新たな問題を生むことになる。地元の運動団体と財団法人に結成段階からかかわり、辣腕をふるってきた小西氏に、所属団体メンバーは結 果的にすべてを任せ、氏の公私混同を許す結果となった。解放同盟の支部大会が長年開かれなかったのは、小西支部長に任せておけばうまくいくという暗黙の了 解があったからこそであろう。
就職のあっせんから夏祭りの資金、お年寄りの団体旅行の経費にいたるまで多くの人が小西氏の世話になった。しかしその資金の一部は、違法に稼いだ金でもあった。

「金がなかったらな、人を助けるなんてでけへんねん」
金を儲けて社会に見返しをしたかったと報道されましたが…と私が問うと、小西氏はそう答えた。社会活動には経済的基盤が必要という現実主義者でもあった。
彼の中では、部落解放運動と違法な蓄財は矛盾していなかったのではないか、と私は思う。稼いだ金を地元住民や出入りの業者・行政職員にもばらまき、自ら のポケットにも入れた。一家の長であるからこそ、“家”の金を好きなように使うことができた。家長は、見方を変えれば、子分を抱えた“お山の大将”でもあ る。誰も逆らう者はいない。その結果、財団法人の収益金を横領するという暴走を許すことになった。
土地ころがし、ヤミ金融、脱税などで実業家となった小西氏は、別の顔を持つ。高齢者や子供、障害者の施設を開所し、社会的弱者のための活動もおこなっ た。しかし、社会福祉法人の理事長の肩書を使い、不動産業などの稼業にも精を出していた。経済活動(金儲け)のために社会活動をしていた、と見えなくもな い。だが、貧しい部落に生まれ育ったことや実子が重度の障害をもつことなどを考え併せると、すべてを金儲けと断じることはできないのではないか。
社会福祉活動を始めた遠因について、小西氏は次のように話していた。
「刑務所に出たり入ったりしとったころ、母親に『お前のために親きょうだいは困ってる。ちょっとはまともな人間になれ』と言われた。その言葉が始終頭にあったわけや」
福祉は儲かる。年寄りは何もわからなくなっているから、体を洗うのはホースで水をかけとけばいい――小西氏がそう語ったとされる新聞報道には、心底怒っていた。名誉毀損で訴える、と息巻いていた。
部落解放運動も他の活動も金儲けのため――。検察や警察の主張を受け入れたマスコミは、そのように喧伝した。はたしてそうなのだろうか。小西氏を弁護するつもりは毛頭ないが、悪人を強調するあまり、社会活動をすべて金儲けに結びつける報道は、あまりにもひどいと思う。
「盗人にも三分の理があるんやっちゅうねん」
取材中、何度もそう言っていた。盗人を自認しているところが、すこし可笑しかった。
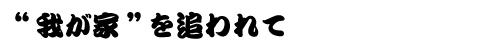
逮捕からわずか1年半後の死だった。北新地の別宅から運転手付きの高級外車で飛鳥に通勤していた小西氏 は、逮捕後は解放同盟支部長と飛鳥会理事長の職を離れ、もはや家長ではなくなった。裁判所の決定で、飛鳥の地に足を踏み入れることさえ禁じられた。「飛鳥 会がある建物はワシの名義や。なんでそこに行かれへんねん」と怒っていた。彼にとって、飛鳥はまだ“我が家”だったのだ。
死の7カ月前のインタビューで、高級棺桶を買ったいきさつについて聞いた時、次のような答えが返ってきた。
「ワシは嫁はんや子供には贅沢させた。ワシも新地で毎晩飲んで歩いた。けれどもな、あの(儲けた)ゼニな、ひとりではなかなか使われへんで。ぎょうさん 寄ってきて、おこぼれ持っていったやないかい。500万円で棺桶をつくったのは事実。あれはワシが死んでいく時のせめてもの贅沢や」
「せめてもの」という言葉は、本来は贅沢をしていなかった人間が使うはずである。
極貧生活から逃れるようにムラを出て、たどりついた飛鳥の地。地元の主となり、権勢をふるった男の最晩年は、逮捕、病気、愛着ある地域からの追放…とあ まりにもみじめだった。それはあたかも、差別と貧困をはねのけるべく興り、相次ぐ不祥事で信用を落とした部落解放同盟と軌を一にしている。皮肉にもその幕 を開けたのが小西氏であった。
贅沢な棺桶は、部落解放運動の闘士には似合わない。豪華な乗り物とともに、小西氏は被告のまま灰となった。

