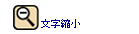
「男・女」「若い・年輩」などの“柵”の中に自分を入れて、「居心地が悪いなあ」と思った経験、ありませんか。今回の登場は、「居心地良く暮らすために、立ちはだかる柵をなぎ倒してきた」と言う桂あやめさん。数少ない女性の落語家の1人です。「良い居心地」の獲得は、努力と経済的自立、仕事責任の全うをしてこそ・・。そんな考えが言外に見えかくれするあやめさんの話を伺います。
足を踏み入れたくなる「男の世界」
女性差別に遇った経験? 私自身はあまり感じたことがないのですが、自分が居心地のいい状態でいたいとずっと思ってきました。だから、居心地を悪くさせる柵をバンバンなぎ倒してきた、と言えるかもしれません。
たとえば、子どもの頃。グリコのキャラメルを買いに行くと、「女の子向きはこっちよ」と店のおばちゃんに言われる。でも、自分が欲しいのはプラスチックの自動車が入っている男の子向きの方だから、そっちを選んだし、服も「男の子用」と言われるジーパンやジージャンを着て、短い髪で野球帽をかぶりたかったので、そんなスタイルを通してきた。サッカーサークルに入れるのは男子だけと聞いて「何で?」と思った小学校の時は、「ほな、作ろう」と女子サッカー部を作ったし、卓球をしたかったのに女子卓球部がなかった中学の時も、顧問の先生を探してきて自分たちでクラブを作りました。
思うに、「ここからは男の世界よ」と言われると足を踏み入れたくなるし、「女の世界はないよ」と言われると自分で作りたくなる性格。落語の世界に入ったのも、何人もの人に「男の人だけの世界よ」と言われたことと関係しているかもしれません。
一カ月で車の免許を取って入門
 私が落語界に入ったのは、18歳の時。文枝師匠と話をさせていただくチャンスが巡ってきた時、「今、免許を持っている弟子がいないので、車が眠ってるんや」と聞いたので、「ほな、免許を取って来ますから、弟子にさせてください」と言って、大急ぎで島根県の合宿免許教習所に通って、必死で免許を取った。そして、1カ月後には、「師匠、免許を取ってきましたんで、今日から弟子になります」と押しかけ、入門させてもらったんです。
私が落語界に入ったのは、18歳の時。文枝師匠と話をさせていただくチャンスが巡ってきた時、「今、免許を持っている弟子がいないので、車が眠ってるんや」と聞いたので、「ほな、免許を取って来ますから、弟子にさせてください」と言って、大急ぎで島根県の合宿免許教習所に通って、必死で免許を取った。そして、1カ月後には、「師匠、免許を取ってきましたんで、今日から弟子になります」と押しかけ、入門させてもらったんです。
その頃、私は落語の世界がどんなものなのか、全然分かっていなかった。男の世界だと言われても、「まあ、やれるわぁ、女も」ぐらいにしか思わず、動物的な勘で選んだようなものです。でも、今から考えれば、文枝師匠を選んだことをはじめ、なかなかの選択だったと思う。


