人権啓発DVDの紹介
2025/05/12
このページでは、大阪同和・人権問題企業連絡会の協力により、人権啓発DVDを紹介します。
INDEX
(№1)カンパニュラの夢
(№2)日頃の言動から考える職場のハラスメント
(№3)夕焼け<
(№4)シリーズ映像で見る人権の歴史 第10巻
差別のない社会へ -私たちはどう生きるか-
(№5)人権のすすめ ハラスメント編、いろいろな性編、障害者編
(№6)あなたの笑顔がくれたもの
(№7)バースディ
(№8)ハラスメントの裏に潜む無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)
(№9)ビジネスと人権 第1巻 ビジネスと人権 マルっと理解しよう!
(№10)大切なひと
【制作協力】大阪同和・人権問題企業連絡会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№1)カンパニュラの夢

1.テーマ 超高齢化社会とひきこもり(8050問題)
2.教 材
(1)タイトル カンパニュラの夢
(上映時間:36分 字幕・副音声付)
(2)制 作 企 画 兵庫県・公益財団法人兵庫県人権啓発協会
企画協力 兵庫県教育委員会
制 作 神広企画株式会社
制作年 2020年
定 価 80,000円(税抜)
問合わせ先 神広企画株式会社 営業部(078-360-6336)
【URL】 https://www.shinkoukikaku.com/jinken2020/
【予告編】 https://youtu.be/4DU62GzMnAE
(3)内 容
本作は、岸本家と谷口家のふたつの家族の視点で進行する。
谷口誠一は自宅に20年以上ひきこもっている。両親と同居しているが、できるだけ顔を合わせないように窮屈に暮らしている。岸本麻帆は、娘が高校生になったことを機に、近所の喫茶店「カンパニュラ」でパートとして働き始める。近所づきあいの中で「(谷口家の)息子さん、ずっと働いていないみたいなの。気をつけて」と言われる。
ある日、麻帆は、裏手にある谷口家から「出ていけ」という怒鳴り声や大きな物音を耳にする。翌日、麻帆は谷口洋子(誠一の母)に思い切って話しかけ、洋子の相談にのる。誠一がひきこもっていること、どうすればいいか分からず、不安を抱えていることなどを聞き、何か自分にできることはないかと考え始める。
インターネットでひきこもり支援センターのことを調べた麻帆は、洋子に紹介し、支援センターで洋子は相談にのってもらう。また、麻帆はケガをした娘が自宅にこもりがちになったことをきっかけに、「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることだと気づく。そこで喫茶店マスターの引田啓介と共に、ひきこもりの方を集めて交流する「ひきこもりオフ会」を企画する。
誠一は、洋子から支援センターや喫茶店イベントの話を聞くが、それでも動こうとしない。オフ会は何度か開催されて参加人員も増えてきた。引田のブログで「がんばらなくてもいい。楽しく過ごすだけでいい」という言葉を見た誠一は、一度参加してみることにする。
3.ねらい
「80代」の高齢の親が、ひきこもりが長期化した「50代」の子を支えている家族が増加しており、親子ともども生活が困窮するなどの課題を抱え、超高齢化社会における新たな社会問題「8050問題」がテーマとなっています。
背景には、家族や本人の病気、親の介護、離職(リストラ)、経済的困窮、人間関係など、複合的な課題を抱えながらも、親子共倒れの問題が発生するまでSOSの声を上げることができない、現在の超高齢化社会における「家族の孤立」が地域に潜在化していることがあります。
主人公はあることをきっかけに「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることだと気づき、この問題に寄り添い、解決策を求め行動を起こします。
一家族の問題とされがちな「8050問題」ですが、誰にでも起こりうることと認識し、理解を深め、地域の人々がひきこもりなどの悩みを共有し偏見をなくすとともに、互いに助け合うことで地域共生社会の実現を考えていくために有用な作品です。
4.話し合いのポイント
①超高齢化社会とひきこもり「8050問題」に対して、話し合ってみましょう。
②地域共生社会をめざして、私たちが日常生活の中で心がけることについて、考えてみましょう。
以 上
【参考資料】
■ひきこもり支援推進事業について
ひきこもりに特化した専門的な相談窓口としてすべての都道府県および指定都市などに「ひきこもり地域支援センター」を設置しています。社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つ支援コーディネーターが中心となって電話や来所等による相談支援を行うほか、同じ悩みを持つ方が集まる居場所を提供したり、ご家族への相談支援等を行っています。
また、ひきこもり支援の核となる、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業」(2024年度110自治体)のほか、ひきこもり支援の導入として、8つのメニュー(相談支援、居場所づくり、連絡協議会・ネットワークづくり、当事者会・家族会開催事業、住民向け講演会・研修会開催事業、サポーター派遣・養成事業、民間団体との連携事業、実態把握調査事業)から任意に選択し実施する「ひきこもりサポート事業」(2024年度154自治体)による取り組みも開始しています。
さらに、都道府県が市町村をバックアップする機能の強化策として、市町村と連携したひきこもり地域支援センターのサテライト設置と小規模市町村等に対して財政支援と支援手法の継承を行う事業も創設し、都道府県の圏域内どこでも支援が受けられるよう平準化を図りながら、市町村のひきこもり支援体制の整備を促進していくこととしています。
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html (厚生労働省「ひきこもり支援推進事業」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№2)日頃の言動から考える職場のハラスメント

1.テーマ 職場のハラスメント
2.教 材
(1)タイトル 日頃の言動から考える職場のハラスメント
(上映時間:29分 字幕・副音声/解説書・ワークシート付)
(2)制 作 企画・制作 東映株式会社 教育映像部
制作年 2021年
定 価 66,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233596_3490.html
【予告編】https://youtu.be/RMX63KBaTV0
(3)内 容
相手の人格を否定しない
指導の対象はミスの原因と再発防止であり、ミスをした者の人格否定ではない。適切な指導を行うためにはどのようなことを意識すればよいのかを考える。
説明とフォローがハラスメントを防ぐ
上司は部下の成長を思い助言をせずに見守ることに徹するが、かえって部下を追い詰めハラスメントと受け止められる。すれ違いが生じないためのポイントを解説する。
業務の適切な範囲を考える
勤務時間外でも送られてくる上司からのメール。返信不要の内容であっても届くたびに負担を感じる部下もいる。事例をもとに「業務の適正な範囲」について考える。
プライバシーを尊重する
先輩からプライバシーに関わる話題を聞かれる後輩。職場で私的なことに過度に立ち入るのはハラスメントになり得る。受け手がどう感じるかを考える。
自分が持つパワーを自覚する
パワハラは上司から部下だけでなく、さまざまな状況で起こり得る。誰でも加害者になり得ること、自分がもつパワーを自覚する。
さまざまな働き方を認める
介護休業や育児休業は法律で認められた権利ではあるが、忙しい同僚から心ない言葉をかけられる。気持ちよく制度を利用するためのヒントを解説する。
職場でハラスメントを受けたら
自分が職場でハラスメントを受けたとき、周囲で見かけたときの対応を考える。
3.ねらい
職場において日頃の何気ない言動がハラスメントにつながることがあります。誰もがハラスメントの被害者にも加害者にもなり得るのです。ハラスメントを防ぐためにはどのようなことを意識すればよいのでしょうか。
本作品は7つのチャプターから構成され、厚生労働省のハラスメントの類型に照らし合わせながら、職場で起こりがちなハラスメントやそのグレーゾーンについて、上司や部下のプライベートの観点、さまざまな働き方などを題材にした事例をもとに考え方のポイントを解説しています。ハラスメントが起こりにくい働きやすい職場環境づくりについて、自分事として考えることができる教材となっています。
4.話し合いのポイント
①自分に思い当たることはないか、周囲に気になる行為や言動はないか話し合ってみましょう。
②働きやすい職場づくりのために私たちができることについて考えてみましょう。
以 上
【参考資料】
■職場のパワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
【URL】https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
(厚生労働省 明るい職場応援団「ハラスメントの定義」)
■職場のハラスメントに当たりうる行為の6類型
「職場のハラスメントに当たりうる行為」として、6類型に分類することができます。
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
これらの例は限定列挙ではありません。また、個別の事案の状況等によって判断が異なることもありえますので、職場におけるパワーハラスメントに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど適切な対応をお願いします。
なお、上記の例については、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。
【URL】https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
(厚生労働省 明るい職場応援団「ハラスメントの類型と種類」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№3)夕焼け

1.テーマ ケアラー ~だれもが人権尊重される社会を~
2.教 材
(1)タイトル 夕焼け
(上映時間:35分 字幕・副音声付)
(2)制 作 企 画 兵庫県・公益財団法人兵庫県人権啓発協会
企画協力 兵庫県教育委員会
制 作 東映株式会社
制作年 2021年
定 価 80,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233596_3490.html
【予告編】https://youtu.be/zeLMTUq4QaU
(3)内 容
主人公の青野瑠依は中学二年生。放課後になると友だちとのおしゃべりも早々に切り上げて、家路を急ぐ。帰宅すると、家事や弟の世話をしている。父親は病気で入退院を繰り返していて、母親が日夜働いて家計を支えている。弟を迎えにいった帰り道、小学校の時の担任の佐藤 灯(ともる)と再会するが、足早に立ち去ってしまう。
灯は、かつて正式採用をめざして教員として働いていた。しかし、親代わりだった祖母が認知症になったことで離職し、介護中心の生活を続けてきた。祖母が他界し、就職活動を始めようとする灯だが、三年の空白が重荷になり二の足を踏んでいる。ある日、灯の祖母が通っていた美容室の店主、世良歌絵が訪ねてくる。夫を介護してきた歌絵は、灯の心境を理解し、寄り添う。
テスト当日、瑠依は、弟の荷物を忘れて困っているところに、灯と友だちの母親が通りかかり、手を差し伸べる。そして灯は、瑠依の家庭の事情を知る。
灯から話を聞いた歌絵が、瑠依は「ヤングケアラー」ではないかと言う。今の瑠依の状況をかつての自分に重ねる灯。そんな灯に歌絵は「ケアラーをケアする居場所」というカフェの企画を進めていることを告げ、手伝ってくれないかと誘う。
さまざまな出来事が重なり、溜め込んだ不安と自己嫌悪から公園で落ち込む瑠依。その姿を見かけた灯は思わず声をかける。灯は自身の経験から「一人で頑張るのはしんどかった。助けてって言えればよかった」と語った。その言葉は瑠依の心に響く。
瑠依の力になりたいと考えた灯は歌絵に、カフェで、子どもたちの学習支援もできないかと提案して・・・。
3.ねらい
この物語の主人公・瑠依は、幼い弟の世話や家事に追われる生活にしんどさを感じつつも、「家族のことは家族でするのが当たり前」という思い込みから、気持ちを押し殺して生活しているヤングケアラーです。しかし、小学校時代の担任であり元ケアラーの灯との交流により、自分の状況や本当の気持ちについて見つめ直し、将来に向き合うための一歩を踏み出します。
本作品は、お互いを気にかけ、人と人がつながっていくことが、ケアラーとその家族が抱える問題解決の糸口になる様子を描いています。ケアは他人事ではありません。年齢属性を問わず、ともに助け合える「だれもが人権尊重される社会」の実現をめざすことを学ぶことができる教材になっています。
4.話し合いのポイント
①ヤングケアラーについて、話し合ってみましょう。
②「だれもが人権尊重される社会」をめざして、私たちが日常生活の中で心がけることについて考えてみましょう。
以 上
【参考資料】
■ヤングケアラーとは
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子どものことをヤングケアラーといいます。
厚生労働省において文部科学省と連携し実施された「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(2020年度調査)では、公立中学2年生の約17人に1人、公立の全日制高校2年生の約24人に1人が「世話をしている家族がいる」と回答し、1学級につき1~2人のヤングケアラーが存在している可能性があることが分かりました。
2024年6月「子ども・若者育成支援推進法」が改正され、これまで法律上の明確な規定がなく、支援も地域によってばらつきがあったヤングケアラーについて、国や自治体が支援を行う対象とすることが明記され、支援の第一歩が始まりました。
【URL】https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/(こども家庭庁「ヤングケアラーについて」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№4)シリーズ映像で見る人権の歴史 第10巻
差別のない社会へ -私たちはどう生きるか-
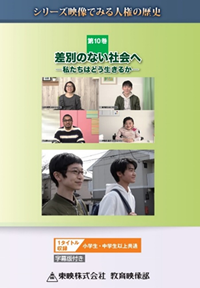
1.テーマ 同和問題(部落差別)
2.教 材
(1)タイトル シリーズ映像で見る人権の歴史 第10巻
差別のない社会へ -私たちはどう生きるか-
(上映時間:20分 字幕付/解説・指導の手引・資料類付)
(2)制 作 企画・制作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
監 修 上杉 聰・外川正明
制作年 2022年
定 価 66,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233607_3490.html
【予告編】https://youtu.be/JaFIqiiQ2bo
(3)内 容
プロローグ ―いやだと言えない―
遊び帰りのアキラと友だち2人が楽しそうに話しながら歩いていると、マサヤを見かける。「うざいから、無視して通りぬけようぜ」と言って、わざとマサヤにぶつかって通り過ぎる。アキラがマサヤを排除する理由を尋ねても、「当たり前」「みんな言っている」と返され、さらに「お前もあいつと一緒なのか」と言われるとアキラはなにも言えなくなってしまう。
第1章 差別ってなんだろう
翌日、アキラはユキとカナに呼び止められ、マサヤに対するいじめだと追及されているところに、やってきた児童館のコウジから、子どもたちが改めて差別の歴史を学ぶこととなる。コウジは「仲間外れにするのが差別なんだ」と諭し、差別をなくす取り組みとして、全国水平社創立以降の部落解放の歩みを説明する。コウジは中学生の頃、叔父の結婚をめぐって部落差別を体験し、差別の現実に出会いながら何もできなかった自分を見つめたことから、人権問題を学んでいることを話す。コウジは、アキラとユキ、カナに児童館でさまざまな差別と向き合っている人たちとの出会いの場を用意することを提案する。また、コウジはアキラにマサヤを誘うように言う。
第2章 差別してるって気づいていない
子どもたちは、被差別部落出身者、電動車椅子ユーザー、在日コリアン3世、日本人とアメリカ人のダブルの4人のゲストティーチャーを招いたオンライン学習を通じて、社会にあるさまざまな差別に気づき、 自分自身を見つめ直し、「差別は差別する側の問題」、人はいじめるものでも差別するものでもなく、尊敬し合うものであることに気づく。
エピローグ ―かっこよく生きる―
児童館からの帰り道、4人はマサヤをいじめていた2人と出会う。「お前、マサヤと同類になったのか」と言われたアキラは決然と「僕らは尊敬し合って、かっこよく生きるって決めたんだ」と宣言する。
3.ねらい
全国水平社創立以降、差別をなくそうとする人々の努力が続けられ、戦後、日本国憲法のもと、基本的人権の実現を求めた部落解放運動の取り組みがなされてきましたが、今もなお差別は存在しています。また、現代社会において、部落問題以外でも、さまざまな差別が存在しています。
本作品は、子どもたちが直面したいじめをきっかけに、ゲストティーチャーを招いたオンライン学習を通じて、子どもたちが社会にあるさまざまな差別に気づき、 自分自身を見つめ直し、よりよい生き方をめざす姿を描いています。子どもたちに、差別を許さない生き方はどうあるべきか、現代社会に残る差別を解決していくために自分はなにができるかを考えてもらうドラマ形式の教材です。
4.話し合いのポイント
①部落差別の歴史を学び、現在のインターネット上の差別、結婚差別の実態を学習しましょう。
②さまざまな差別の実態を知り、現在の法律のあり方、ダイバーシティやSDGsの理念「誰ひとり取り残さない」社会、などについて理解を深めましょう。
以 上
【参考資料】
■映画「破戒」
2022年3月全国水平社創立100周年となる年に島崎藤村の不朽の名作「破戒」が60年ぶりに映画化されました。被差別部落出身という出自を隠し小学校の教壇に立つ教師の主人公・瀬川丑松。故郷を離れてもつきまとう自らの出自に葛藤する姿が描かれ、主演の間宮祥太朗が苦悩しながらも、生きていく主人公を演じました。
この映画から部落差別における、①歴史的背景の理解、②主人公の葛藤、③差別の現実、④解放運動の重要性、⑤現代への問いかけ等が学習できる作品です。現在、Blu-ray、DVDや動画配信サービス等で視聴することができます。
【URL】https://www.toei-video.co.jp/special/hakai-movie/(東映ビデオオフィシャル「破戒 特集」)
■日本の人権課題とは
法務省の人権擁護機関では、①女性、②こども、③高齢者、④障がいのある人、⑤部落差別(同和問題)、⑥アイヌの人々、⑦外国人、⑧感染症、⑨ハンセン病患者・元患者やその家族、⑩刑を終えて出所した人やその家族、⑪犯罪被害者やその家族、⑫インターネット上の人権侵害、⑬北朝鮮当局によって拉致された被害者等、⑭ホームレス、⑮性的マイノリティ、⑯人身取引、⑰震災等の災害に起因する人権侵害の17項目を2024年度の啓発活動強調事項として挙げて、人権啓発活動を実施しています。
これらの人権課題に対して、①教育と啓発、②ボランティア活動、③声を上げる、④多様性の尊重、⑤政策への参加、⑥持続可能な開発目標(SDGs)への取り組み等を通じて、私たち一人ひとりが人権課題の解決に向けて貢献できるのです。
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00005.html(法務省「啓発活動強調事項」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№5)人権のすすめ ハラスメント編、いろいろな性編、障害者編

1.テーマ 職場のハラスメント・いろいろな性・障がい者
2.教 材
(1)タイトル 人権のすすめ ハラスメント編、いろいろな性編、障害者編
(上映時間:25分 字幕・副音声/解説書・ワークシート付)
(2)制 作 企画・制作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
制作年 2022年
定 価 70,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233602_3490.html
【予告編】https://youtu.be/ItOxRKnlDls
(3)内 容
「ハラスメント編」 テーマ:ジェンダーハラスメント
桜井恭平は、妻の妊婦健診の付き添いで仕事を休む旨を部長の前原に伝える。すると部長に「イクメンも良いが女性陣に負けないように、男なら仕事も育児も両方"欲張り″にこなすべき」と伝えられる。一方、妻には「両方はなぜ欲張り」「女性を見下している」「仕事を頑張るのに性別は関係ない」と言われ、部長の発言に違和感を覚えた。
「いろいろな性編」 テーマ:性のあり方
坂原健斗は先輩の水越早紀とともに、職場のトランスジェンダーであることをカミングアウトしている佐伯 淳に対して、社内の人権研修の一環でインタビューを行う。取材の冒頭で佐伯から『性のあり方』を尋ねられ戸惑ってしまう。佐伯は、「男性として振る舞う毎日に心がすり減り、仲間をだます自分が許せなくなった」ある日勇気をもって信頼できる数名に「カミングアウトして気持ちが楽になった」と言う。
「障害者編」 テーマ:無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)
平野大樹の部署に配属された松岡朱里は視覚に障がいがあり、左目は義眼で右目は進行性の弱視だ。休憩室で同僚の武藤塔子と3人、昼食を取りながら松岡の休日の過ごし方など何気ない会話をしていると、「写真展にはまっています」「一人暮らしです」の言葉に、つい褒め言葉のつもりで「何でも一人で出来てすごい」と発言してしまう。
3.ねらい
性別による固定観念・役割分担意識から「男は仕事」「女は家事」などと決めつける古い考え方が、人を傷つけたり、プレッシャーを与えたり、無意識のジェンダー差別につながります。
この作品は、職場における「ハラスメント」「いろいろな性」「障害者」をテーマに取り上げ、それぞれのテーマの「気づき」を通して、多角的に人権問題について考えます。
4.話し合いのポイント
①ジェンダーハラスメントにあたる言葉を見聞きしたことがありますか?
②一人ひとりの「性のあり方」の決めつけには、どのようなものがあるのでしょうか?
③「障がい者は健常者より劣っている」という考え方や決めつけをしてしまっていることはないでしょうか?
以 上
【参考資料】
■多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて
「SOGI」とは、「性的指向(Sexual Orientation)」と「性自認(Gender Identity)」の頭文字をとった略称です。
「性的指向」とは、恋愛または性愛がいずれの性別を対象とするかをいうものです。ご自身と異なる性別の人を好きになる人、自分と同じ性別の人を好きになる人、相手の性別を意識せずにその人を好きになる人などがいます。また、誰にも恋愛感情や性的な感情をもたない人もいます。
「性自認」とは、自己の性別についての認識のことをいいます。生物学的・身体的な性、出生時の戸籍上の性と性自認が一致しない人を「トランスジェンダー」といいます。生物学的な性が男性で性自認が女性、生物学的な性が女性で性自認が男性といった場合があります。また、身体的な性に違和感を持つ人もいます。この状態に関して医学的には「性同一性障害」と診断される場合があります。
性的指向や性自認は、本人の意思で選択したり変えたりできるものでも、矯正したり治療したりするものでもなく、個人の尊厳に関わる問題として尊重することが大事といえます。
【URL】https://www.mhlw.go.jp/content/000808159.pdf
(厚生労働省「多様な人材が活躍できる職場環境づくりに向けて~ 性的マイノリティに関する企業の取り組み事例のご案内 ~」)
■これからは、「ユニバーサルマナー」の時代!
私たちの社会には、いろいろな人が生活しており、お互い関わり合いながら共存しています。まちでは、高齢者や障がい者、外国人など、多様な方々を見かけます。このように、多様な他者の立場を考え、広い(ユニバーサルな)視点で向き合うためのマインドとアクションが「ユニバーサルマナー」です。言語や国籍、年齢や性別あるいは障がいの有無にかかわらず、誰にとっても利用しやすい製品、施設を「ユニバーサルデザイン」を呼ぶのと同様に、多様な方々に対する心づかいや行動を「ユニバーサルマナー」と呼んでいるわけです。この用語を初めて聞いた人も多いでしょうが、大事なのは用語でなく、あくまで心づかいの行動です。
【URL】https://www.pref.nara.jp/secure/265834/05koramu.pdf
(奈良県「ユニバーサルマナー」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№6)あなたの笑顔がくれたもの

1.テーマ 周りから見えにくい障がい・生きづらさ
(発達障がい・ヤングケアラー・障がい者)
2.教 材
(1)タイトル あなたの笑顔がくれたもの
(上映時間:37分 字幕・副音声付/解説書・ワークシート付)
(2)制 作 企画・制作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
制作年 2022年
定 価 70,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233601_3490.html
【予告編】https://youtu.be/6xiTNFP5y0o
(3)内 容
美容メーカーでチームリーダーを務める麻友子は、久しぶりに会う幼馴染の紗希から結婚の報告とともに発達障がいであることを告白される。麻友子は「発達障がい」という言葉に対する思い込みから「そんなふうに見えない」「実は天才だったりして」と励ますが、紗希は困惑した表情で言葉をなくす。
麻友子と同じチームで働く後輩の桃田は仕事が早く、いつも定時になるとすぐに帰っている。社内コンペに向けて親睦会を企画するも、桃田だけは「業務でないなら」と参加には消極的で、他の社員から「ノリが悪い」と非難される。
ある日、麻友子は公園の多目的トイレでポーチを拾ったことからオストメイト(人工肛門保有者)である女子高生の美織と出会う。周りにはオストメイトであることを隠さず伝えているという美織に対し「強いね」と口にする麻友子だが、「そう見えるだけかもよ?」と複雑な表情を浮かべる美織。
それからしばらくして、介護用おむつを持って歩いていた桃田と鉢合わせした麻友子は、桃田が認知症の祖母の介護をしていることを知る。そして、自身も小学生のころ桃田と同じような境遇だったことを思い出す。
麻友子から当時の話を聞いた美織は「ヤングケアラーだったんだね」と一言。麻友子は初めてそういう言葉があることを知る。美織との会話を通じて、紗希や桃田に対してきちんと向き合えていなかったことに気づいた麻友子は2人とあらためて話すことを決意する。
3.ねらい
「人権」は日常の何気ない人と人との関係性の中にもあります。しかしながら、家族や友人、同僚などの近く親しい関係性においては、相手を一人の人間としてその人権を尊重する意識がおろそかになってしまうことがあります。
主人公の麻友子は、発達障がいである親友の紗季、オストメイトの女子高生美織、祖母の介護をしている桃田、それぞれ周りからは見えにくい生きづらさを抱えている3人との関わりにより、自分の思い込みに気づきます。
外見で決めつけたり、「障がい者」や「ヤングケアラー」などカテゴリーで人を判断したりせず、一人ひとりが考えや感じ方も違う人間であるということを理解して向き合うことの大切さを学ぶことができる教材です。
4.話し合いのポイント
①麻友子は、紗希、桃田、美織との交流を通じて、どんなことに気づき、どのように変わろうと考えたでしょうか。
②もしあなたが「周りから見えにくい障がいや生きづらさ」を抱える立場になったら、どのような悩みが出てくると思いますか。また、その悩みを誰かに相談しようと思いますか。
③誰もが悩みや生きづらさについて相談しやすい環境をつくるためには、どうしたらいいでしょうか。
以 上
【参考資料】
■「周りから見えにくい障がい」について
見た目にはわかりにくい、伝わりにくい障がいはいろいろあります。ここではその一部を紹介します。
・聴覚障がい・・・聴覚機構の障がいで聞こえの機能が低下している状態
・内部障がい・・・呼吸機能障害、心臓機能障害、膀胱又は直腸の機能障害(ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を必要とする疾患)、HIVほか
・発達障がい・・・知的障害(知的能力障害)、コミュニケーション障害、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(限局性学習症、LD)、発達性協調運動障害、チック症
【URL】https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000100678.pdf
(市川市「見た目にはわかりにくい、伝わりにくい障害は様々です。」)
【URL】https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-049.html
(e-ヘルスネット(厚生労働省)「発達障害」)
■「ヘルプマーク」について
外見からはわからない援助や配慮を必要としている方々(義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など)が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都福祉保健局で作成したマークで、現在では全国の自治体や企業等でも普及活動がされています。
このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
【URL】https://www.pref.osaka.lg.jp/o090050/keikakusuishin/helpmark/index.html
(大阪府「ヘルプマークについて」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№7)バースディ

1.テーマ 性の多様性を認め合う
~誰もが自分らしく生きられる社会をめざして~
2.教 材
(1)タイトル バースディ
(上映時間:37分 字幕・副音声付)
(2)制 作 企 画 兵庫県・公益財団法人兵庫県人権啓発協会
企画協力 兵庫県教育委員会
制 作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
制作年 2022年
定 価 80,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】
https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233604_3490.html
【予告編】https://youtu.be/Trj3-NqTPng
(3)内 容
羽野美由紀は、20歳になる娘の笑花(えみか)が"女らしい"振る舞いをしないことが不満だった。笑花は誕生日の夜、自分がトランスジェンダー男性(自認する性が男性)であることを両親に打ち明ける。性別違和ゆえに小さい頃からずっと辛かったこと、将来は手術もしたいと考えていること、そして、これからは名前を「尊(たける)」(以降は表記を「尊」に統一)に変えて生きていくことを決意して告げる笑花。突然のカミングアウトに動揺する美由紀たち。尊の気持ちを受け止めることができない美由紀は翌日から尊を避けるようになる。
上司の玉木や同僚からの理解もあり、職場では自分らしく働ける尊。一方、誰にも相談できずに悩んでいた美由紀は、何かを抱えていることを同僚の祐奈に見透かされ、「友達の娘が」ということにして相談し、少し気持ちが軽くなる。
数日後、先輩が尊のことをアウティング(本人の性の在り方を同意なく第三者に暴露)してしまう。不安と恐怖から早退する尊。ただ事ではない様子で帰宅してきた尊を見た美由紀は、心配ゆえに、女性のままでいるように懇願し、かえって尊を傷つけてしまう。尊は家を飛び出していく。
上司の玉木の協力もあって、尊は無事に見つかり、安心する美由紀。そして、玉木や祐奈の考え方に触れ美由紀は、次第に自分の心と向き合っていき・・・。
3.ねらい
性的少数者については、依然として社会理解が進まず、偏見や差別、配慮に欠けた対応などで、自身の思いや悩みを打ち明けることが難しく、周囲の無理解に苦悩し、生きづらさを感じている状況などさまざまな問題があり、深刻な人権問題になっています。
一方、性的少数者であることを打ち明けられた家族や友人、職場の同僚などは、偏見や知識不足によって、理解しようと向き合う前に混乱や抵抗感にとらわれてしまいがちです。性のあり方は多様で、性的少数者の存在や悩みに気づくことが大切です。
本作品は、すべての人が自分らしく生きていける社会の実現をめざし、性的少数者について理解するきっかけとなり、多様性と人権を尊重することについて学べる教材です。
4.話し合いのポイント
①性的少数者に対して理解を深めるために、あなたの職場ではどのような取り組みが必要か考えてみましょう。
②あなたが性的少数者からカミングアウトされた場合、どのように対応するか考えてみましょう(家庭、職場、友人など)。
以 上
【参考資料】
■性的マイノリティに関する偏見や差別について
性的マイノリティであることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。
このような偏見や差別を解消するため、労働施策総合推進法に基づく職場におけるパワーハラスメント防止のための指針において、性的マイノリティに関する侮辱的な言動を行うこと等をパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記しているほか、企業の取組事例集等を作成・周知するなど、職場における理解を促進するための取組が進められています。
また、学校等においても、児童、生徒及び学生に対するきめ細かな対応や、適切な教育相談が行われるよう、教育関係者への働きかけが行われています。
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html
(法務省「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう」)
■性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組~
2023年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)」が公布・施行されました。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、これらに関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00007.html
(厚生労働省「性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組~」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№8)ハラスメントの裏に潜む無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)

1.テーマ 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)
2.教 材
(1)タイトル ハラスメントの裏に潜む無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)
職場のコミュニケーション向上のヒント
(上映時間:24分 字幕・副音声付/解説書付)
(2)制 作 企画・制作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
制作年 2023年
定 価 70,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】
https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233611_3490.html
【予告編】https://youtu.be/L9BTfq8pskM
(3)内 容
ステレオタイプ ~気づきを共有する~
ステレオタイプというのは、人の持つ属性(性別、人種、年齢、血液型、学歴など)に関連づけて、先入観や固定観念でその人のことを勝手に決めつけてしまうバイアスです。性別に関するステレオタイプにとらわれた言動は、セクハラやSOGIハラにつながりやすいため注意が必要です。
経験則によるバイアス ~価値観を確かめ合う~
経験則による価値観に固執し、「自分のときはこうだったから」と、それを相手に押し付けてしまうと、パワハラやマタハラ、ケアハラのきっかけになってしまうことがあります。お互いに相手の価値観を確認し合う意識を持つことで、認識のズレを防ぐことができます。
能力の決めつけ ~客観的な視点を意識する~
日々のコミュニケーションの中で、人は無意識に相手の能力を評価してしまっていることがあります。そして、その判断基準にはさまざまなバイアスが影響しています。
偏った判断基準のもと、相手や自分の能力を評価してしまうと、言動がパワハラにつながってしまうことがあります。
3.ねらい
「アンコンシャス・バイアス(Unconscious Bias)」とは、無意識の偏見や思い込みを示す言葉で、その人の先入観により、ものの見方が偏ってしまうことを表します。日常の何気ない言葉や行動に含まれるため、無意識のうちに誰かにストレスを与えてしまい、ハラスメントの行為につながるおそれがあります。
本作品は、職場のコミュニケーション向上のヒントとして、代表的なアンコンシャス・バイアスである「ステレオタイプ」「経験則によるバイアス」「能力の決めつけ」を見える化し、どのようにバイアスに向き合っていくべきか、自分事として考える内容の教材です。
4.話し合いのポイント
①ハラスメントにつながってしまうアンコンシャス・バイアスには、どのようなものがあるでしょうか?
②アンコンシャス・バイアスに気づき、向き合っていくために、どのようなことを意識すればよいでしょうか?
以 上
【参考資料】
■「アンコンシャス・バイアス」は、なくすものではなく、気づくもの
アンコンシャス・バイアスは一部の人にだけあるものではなく、私たちの誰の中にもあって当然のものです。悪意のない思い込みが招いてしまった人間関係のこじれや、仕事のミスなど、誰しも経験したことがあるのではないでしょうか。
ダイバーシティとインクルージョンをテーマとし、多様な個性をいかす社会づくりや良好なコミュニケーションを目指すために、アンコンシャス・バイアスに気づき、向き合うことが求められています。より多くの人びとにその認知を広めるための発信方法を紹介します。
【URL】https://dentsu-ho.com/articles/7617
(ウェブ電通報 電通ダイバーシティ・ラボ「"かくれた思い込み"に気付き、向き合おう~アンバス・ダイアログNo.1」)
【URL】https://dentsu-ho.com/articles/7625
(ウェブ電通報 電通ダイバーシティ・ラボ「"かくれた思い込み"に気付き、向き合おう~アンバス・ダイアログNo.2」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№9)ビジネスと人権

1.テーマ ビジネスと人権
2.教 材
(1)タイトル ビジネスと人権
第1巻 ビジネスと人権 マルっと理解しよう!
(上映時間:36分 字幕選択式/ワークシート付)
(2)制 作 企画・制作 株式会社アスパクリエイト
監 修 影山摩子弥(横浜市立大学教授)
制作年 2023年
定 価 65,000円(税抜)
問合わせ先 株式会社アスパクリエイト(03-5803-9511)
【URL】https://www.asp-create.com/catalogues/view/1405/
【予告編】https://youtu.be/3AgaN_gRg-s
(3)内 容
ABCコーポレーション・サステナビリティ推進室の片山鈴香が「ビジネスと人権」の社内プレゼンテーションの準備に取り組み、父親を相手にリハーサルを行います。
ビジネスと人権、そもそも「人権」とは?
「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年:国連)、「ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)」の策定(2020年:日本)など、企業がビジネスと人権 に取り組む背景や、人権とは英語ではHuman Rightsであり、すべての人が生まれながらに持っている権利であること、また第二次世界大戦後の人権に関する法整備について解説しています。
企業が尊重すべき人権、企業にもたらすネガティブな影響
企業活動によって人権侵害が発生する可能性のある対象や責任の範囲。また人権問題はCSRであり、内部通報制度も含めた人権を支える仕組みづくりの必要性。その仕組みが不十分な場合は経営的なダメージを負うリスクが高まります。
人権デュー・ディリジェンスと救済措置
人権デュー・ディリジェンスとは組織が人権を擁護するためのマネジメントシステムの重要な要素であり、①人権への影響評価、②予防/是正措置の実施、③モニタリング、④情報公開の一連のプロセスを継続的に実施すること、また救済措置の重要性について解説しています。
人権リスクへの取り組み充実によるポジティブな影響
経営の安定や業績アップ、SDGsやESG投資などの対象としての評価につながります。
3.ねらい
そもそもビジネスと人権とは何か?なぜビジネスと人権に取り組むのか?企業にはサプライチェーンも含めた人権への積極的な取り組みや人権デュー・ディリジェンスへの対応が強く求められています。国際的な人権に対する取り組みが不適切な場合は、企業の評判や信頼が損なわれ、法的な問題が生じるリスクを伴いますが、一方、適切に対応した場合は新たなビジネスチャンスや経営の持続可能性を手に入れることにつながることなど、企業が尊重すべき人権やその影響について学んでいきます。
・ビジネスと人権が注目される背景
・ビジネスと人権に関する指導原則
・人権リスクが企業にもたらすネガティブな影響
・企業に求められる人権尊重の取り組み--人権デュー・ディリジェンス など
「ビジネスと人権」について自社でのプレゼンテーションの準備にあたる主人公の視点を通して、企業が人権に取り組む意義についてわかりやすく学べる教材です。
4.話し合いのポイント
①自社におけるビジネスと人権の進捗状況について確認しましょう。
②自分の仕事で起こりうる人権課題について話し合ってみましょう。
③自分の業務で関係するサプライチェーンの現状を確認しましょう。
以 上
【参考資料】
■日本における「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)(2020-2025)の策定について
<National Action Plan on Business and Human Rightsの略>
2011年、国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が決議され、各国には国別行動計画の策定が促されており、また、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に当たっては、人権の保護・促進が重要な要素と位置付けられています。
2020年10月16日、企業活動における人権尊重の促進を図るため、国連の「指導原則」を踏まえた上で、関係府省庁が協力し、日本における「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されました。
【URL】https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104258.pdf
(外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画」(概要))
【URL】https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf
(外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画」(本文))
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(№10)大切なひと
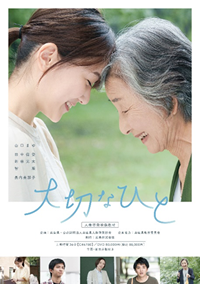
1.テーマ ネット社会における部落差別と人権
~誰もが一人の人間として尊重される社会の実現をめざして~
2.教 材
(1)タイトル 大切なひと(上映時間:34分 字幕・副音声付)
(2)制 作 企 画 兵庫県・公益財団法人兵庫県人権啓発協会
企画協力 兵庫県教育委員会
制 作 東映株式会社 コンテンツ事業部門 教育映像部
制作年 2023年
定 価 80,000円(税抜)
問合わせ先 東映株式会社 営業推進室(06-6345-9026)
【URL】
https://www.toei.co.jp/entertainment/education/detail/1233616_3490.html
【予告編】https://youtu.be/Ptshd_q5lWw
(3)内 容
佐々木愛依(めい)は、大学の友人・大哉(ひろや)が投稿サイトにアップする動画をいつも楽しみにしていた。日本史が好きな大哉は、各地を訪れてその歴史を紹介するチャンネルを運営している。
ある日愛依は、大哉が投稿した動画がバズったと聞く。だがその動画とは、友人・光星(こうせい)からの助言で作られた、かつての被差別部落を訪れ、過激な編集を施したものだった。増え続ける再生回数に喜び、次々に同じような動画をアップする大哉と光星。その中には、在日外国人集落を取り上げたものもあった。コメント欄には差別を煽る書き込みが連なる。複雑な気持ちで動画を見ていた愛依は、そこに映っている家に見覚えがあることに気がついた。
愛依は小学生の頃に父を亡くし、母が働くことになり、いつも愛依を預かってくれたのは母の友人「綾女(あやめ)おばちゃん」だった。愛依のことを本当の家族のように可愛がってくれた綾女。部落だと動画に映っていたのは、その綾女の家であった。
差別や偏見を煽る動画を消してほしいという愛依の切実な想いを聞いた大哉は、すぐに動画を削除する。しかし、第三者によって削除したはずの動画がネット上で拡散されてしまう。殺到する誹謗中傷に困り果てた愛依・大哉・光星の3人は、メディア社会論を専門とする朴優奈(ぱくゆな)准教授に相談をすることに。
朴は、かつて自身の国籍により誹謗中傷を受けた経験を語り、差別の加害者にならないためには「心のアラート」が大切なのだと3人を諭す。心から反省する大哉と光星。
その夜、愛依は実家の母から綾女と連絡がつかないと聞き不安に駆られていた。愛依は過去のある出来事をきっかけに、綾女とはもう長らく会っていなかった。
12年前、幼い愛依が綾女にしてしまったある出来事とは・・・
3.ねらい
現代社会におけるインターネットは利便性が高く、SNSや動画投稿サイトなどを通して自分の意見を自由に発信することができるのが特徴です。一方、インターネット上では他者からの評価が自身の評価と誤認し、部落差別・外国人差別といった偏見や差別を助長するような情報を発信する行為がみられます。ときに投稿者自身も第三者から誹謗中傷を受けることがあり、現在深刻な人権問題となっています。
本作品は、差別のない社会、誰もが一人の人間として尊重される社会の実現をめざし、インターネット上の一部の情報が、誤った認識や差別意識を助長すること、表現の自由を逸脱した許されない行為であると気づく大切さ、差別されている当事者が訴え続けるという負担を強いる社会構造の実態について学べる教材です。
4.話し合いのポイント
①ネットリテラシーについて考えてみましょう。
②表現の自由について考えてみましょう。
③同和問題へのアンコンシャス・バイアスについて考えてみましょう。
以 上
【参考資料】
■インターネット上の人権侵害について
インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、こどもも加害者や被害者として巻き込まれるSNS等におけるネットいじめ、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)、「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。
また、児童ポルノやリベンジポルノは、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害者は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。
さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。
法務省の人権擁護機関では、「インターネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項の一つとして掲げ、 啓発動画の配信や啓発冊子の配布に加え、青少年を中心に深刻化するインターネットによる人権侵害への取組として、携帯電話会社が実施するスマホ・ケータイ安全教室と連携した人権教室を実施するなど、さまざまな啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
(法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」)

