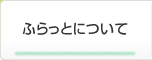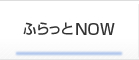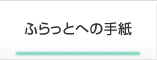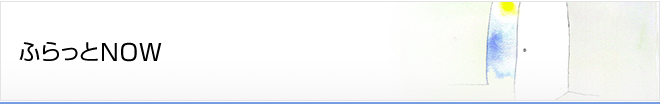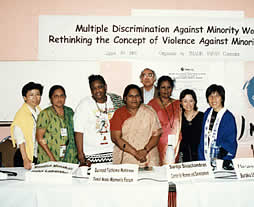部落
- 2002/11/08
重い扉をこじ開け、部落の内側から外側へ 熊本理抄さん -
-

隅っこで悩んでいる子に「おいでよ!」って言いたい
熊本さんが「部落」から逃げ続けてきたひとつの要因に「素敵なサンプルに出会おうとしなかった」ということがある。精神的な面で影響を受けた人がいなかった。
「でもね、私が部落問題や女性問題について語りはじめたら、すごく魅力的な人にたくさん出会えたんです。母や祖母とも『素敵なサンプル』として出会い直すことができました。声を出してつながろうとすると、必ず出会えるってわかった」
いろんな形の部落解放運動を作っている人たちや、部落問題以外の人権問題、市民活動家の女性たちに、いい刺激を受け、成長してきたと思う。
それでも、部落なんていまの時代に関係ない、と言いながらなんとなく自分に自信をもてないでいる人たちが圧倒的多数だ。ことに部落解放運動に関係してこなかった人たちの中には、部落民であることをマイナスイメージでとらえたまま心の内に取り込んでいる場合がある。
「『母が部落出身だから』でも、『部落で育ったから』でもなく、私が私自身や私の生き方を考えていく中で、こういう生き方を選んだし、引き受けたけれど、みんながみんな“部落民”を宣言する必要はないと思う。私も四六時中、部落民を意識してるわけじゃないし。さらっと生きているように見えても、悩んだり迷ったり、ぶつかったり、打ちのめされてはまた元気をもらいながら生きてもいるし」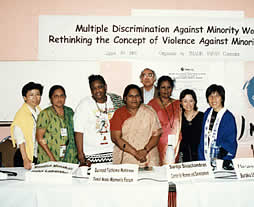
カナダ留学で出会ったマイノリティ社会の問題が、後年ダーバン2001(反人権主義・差別撤廃国際会議)につながっていく。会場にて。右から2人目が熊本さん。 力強く宣言するのでもなく、隠すこともしない。あたりまえに、ニュートラルに「わたしは部落で生まれたんだ」と必要なときに話せるようになれたらどんなに楽だろう。
「わたしがね、そんなサンプルの1つになれたらいいと思うんです。部落で生まれて、いろんな葛藤をかかえて逃げてきて、人権問題に出会って・・・ユニークなのが増えたら、あ、そういうやり方もあるんだって思えるでしょ」
小学生の頃、ともだちになりたいのになれなくて、靴箱の隅でじっと人の輪をながめている子というのが必ずいた。そんな子にいち早く気づいて「おいでよ!」と声をかけたい、と熊本さんは言う。
「部落で生まれて、解放運動を経験してこなかった人たちの中にも、部落問題を話したい人ってたくさんいるはず。いまは、そんな人たちと“とにかく話したい!”。いろんな出会い方があっていいし、いろんな関わり方があっていい。しんどくなったら休めばいい。それが部落解放運動だと思うし、部落出身者が“わたし”を元気に語ることも部落解放のひとつじゃないかな」。
『部落』『部落解放』は、まさに“手垢のついた”イメージばかりが先行している。多くの人々がむやみやたらと触れてはいけない世界だと、避けてきた。外側がこうした勝手な自主規制をかけてきた要因のひとつには、部落の内側から熊本さんのように自由で柔軟な発言をする人が少なかったことにもある。運動経験の有無や部落民であるなしにかかわらず、誰が、どんな立場からでも発言していい。開かれて当然の扉が、古くさい概念で錆びついている。
熊本理抄という女性は、そうした扉をこじ開け部落の内側から外側へ、自由な風を運ぶ人のひとりである。





1972年、福岡県生まれ。6歳の頃から、両親の離婚を機に母のふるさとである部落での生活がはじまる。私立中学卒業後、県立の進学校を経て大学在学中にカナダに留学。卒業後、反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)の専従職員に。2000年2月より事務局長、「マイノリティ女性が世界を変える! マイノリティ女性に対する複合差別」(解放出版社)編集・発行に携わる。2002年春に退職。現在、近畿大学人権問題研究所に勤務。






- 関連キーワード: